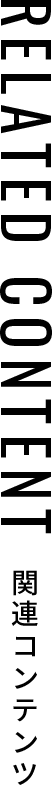佐藤卓己氏(京都大学教授)による『メディアリテラシー 吟味思考(クリティカルシンキング)を育む』の書評を起点に、佐藤氏、坂本旬氏(法政大学教授)、山脇岳志(スマートニュース メディア研究所 所長)の3人が、メディアリテラシー教育の課題、そして、現代のメディアをめぐる可能性と問題点などを、歴史的観点も交えながら今後に向けて語り合いました。モデレーターは、同書の第1章を執筆した藤村厚夫(スマートニュース メディア研究所 フェロー)が務めました。全3回に分けて、お伝えしている議論の第3部。※第1部はこちら、第2部はこちら (以下、敬称略)
<登壇者略歴>
佐藤 卓己
京都大学大学院教育学研究科教授、副研究科長
1960年広島市生まれ、89年京都大学大学院博士課程単位取得退学。東京大学新聞研究所助手、同志社大学文学部助教授、国際日本文化研究センター助教授などを経て、現職。京都大学理事補、京都大学総長首席学事補佐兼務。著書に、『現代メディア史』(岩波書店)、『「キング」の時代』(岩波書店、日本出版学会賞受賞、サントリー学芸賞受賞)、『流言のメディア史』(岩波新書)など多数。
坂本旬
法政大学キャリアデザイン学部教授
1959年大阪府出身。東京都立大学大学院教育学専攻博士課程単位取得退学。専門はメディア情報教育学、図書館情報学。96年より法政大学教員。ユネスコ・メディア情報リテラシーと異文化間対話大学ネットワーク担当。アジア太平洋メディア情報リテラシー教育センターおよび福島ESDコンソーシアム代表。著書に、「メディア情報教育学」(法政大学出版局)、「メディアリテラシーを学ぶ」(大月出版)等多数。
山脇岳志
スマートニュース メディア研究所 所長
1964年兵庫県出身。京都大学法学部卒、朝日新聞社入社。経済部、調査報道担当、オックスフォード大学客員研究員、ワシントン特派員、論説委員、GLOBE編集長、ベルリン自由大上席研究員、アメリカ総局長、編集委員などを経て退職。スマートニュース メディア研究所 研究主幹に。2022年4月より現職。京都大学経営管理大学院特命教授を兼務。編著に『現代アメリカ政治とメディア』(東洋経済新報社)など多数。
藤村厚夫
スマートニュース株式会社フェロー/スマートニュース メディア研究所 フェロー
1990年代を株式会社アスキーで書籍および雑誌編集者、その後ロータス株式会社(現・日本IBM)でマーケティング責任者として過ごす。
2000年に株式会社アットマーク・アイティを創業。2005年に合併でアイティメディア株式会社代表取締役会長。11年同社退任。以後、新たなメディア産業のあり方をめぐる模索を開始。13年にスマートニュース株式会社執行役員。18年より同社フェロー。22年同社メディア研究所フェロー。
教育の現場で「答えがない」と教えることについて
佐藤 第2部でも出ている議論になりますが、メディアリテラシー教育は、効果を追求すればエリート教育にならざるを得ないとも思うのです。わりと思考力の高い子どもたちの前であれば、(先生側も)「私も答えは知りません」「一緒に考えましょう」と気楽に言うことができる。一方で、それがどこでもできるのかと言うと、おそらく難しいのではないでしょうか。
そこで先ほど教育委員会の方々の理解の話がありましたが、「正解はないですよ」ということが、一般的に教育現場では許容されないのではないか、という懸念もあります。
山脇 その点は、佐藤さんと考えが違うかもしれません。
第1部のカリフォルニア大学のジョセフ・カーン教授の調査結果の話で、知識の豊富な若者たち、つまりエリート的な学生とも言えると思いますが、彼らはむしろ自分の持つバイアスに影響され、事実を提示されても、自分の信念と違っている場合には、「不正確だ」と判断する人が多いと示されていました。
トランプ氏も、学歴だけ見たらエリートですよね。エリートに必ず、思考の柔軟性があるわけではなく、むしろ、エリートが自らの能力や知識を過信すると、「落とし穴」にはまりがちです。
メディアリテラシー教育は、メディアのバイアスとともに自分のバイアスを自覚する、自省的で謙虚になることを促すものであって、必ずしもエリートのための教育ではないと思います。
その中で、先生だけがすべて分かっているとなると、それはある種の傲慢さにつながるわけで、「先生にも分からないことがある」のを認めるのは、自然なことであり、むしろ好ましいことではないでしょうか。生徒たちが、「社会は複雑であり、先生にも答えられないこともあるのだ」と知ることは大事なのではないかと思います。
佐藤 ただ、初等中等教育において、答えがないということを教えるシステムが果たして機能しているのか、と懸念します。私は教育方法学を全く知らない人間だから分からないのですが、坂本さん、そのあたりはどうなんでしょう。
坂本 新しい教育をやろうとすると、その問題は学校現場で常に問われています。現場には、「学力を上げてください」という先生もいれば、校長先生もいるわけです。
僕はESD(持続可能な開発のための教育)と呼ばれるユネスコの教育を行っている学校を支援しているのですが、ユネスコスクールの教育は点数が付かないのです。その中身は「探究学習」ですから。
それ自体は文科省の政策なのですが、現場ではうまく行かない、その矛盾が特に小学校の中ではあります。だんだん上の学年に行くにしたがって受験勉強の要素が強くなります、そこに収斂されてしまうのです。ただ、それでも今の伝統的な学校教育では駄目だという意見はたくさんあり、変えなくてはという議論になっています。
では、新しい評価基準はあるのかと言われると、はっきりしない。特に学力以外の部分はとても測りにくいのです。そこで違う測り方として、形成的評価という考え方がありますが、実際それは受験では使えないので、ヨーロッパのように面接試験をたくさん行って長い時間かけて選考するというぐらいのことしかできない。そしてそれは現実的ではないと言われるのです。
だから、そこは非常に難しい問題です。最初に僕が「メディアリテラシーはラジカルであるが、制度化された時にラジカルさをどう残していくのかということが重要だ」と話しましたけれども、常にそのことは問われないといけない課題だと思います。
山脇 しばらく前に、『メディアリテラシー』のオンラインでの出版記念イベントがあり、デジタル時代の教育について書かれた漫画が大きな話題になっている熊本県の前田康裕さん(熊本市教育センター主任指導主事)にも、ご登壇いただきました。その中で、前田さんは「対話を重視した問題解決型の学習に切り替えたあと、思考力を問う問題をやらせたら、全国学力テストでの点数が非常に上がった」と話されていました。授業の中で必ずしも正解を示さなくても、読解力なり思考力が鍛えられていくやり方はあるのではないでしょうか?
坂本 この問題は評価の仕方を新しく考え直そうという流れと連動していると思います。評価方法と教育方法を総体として考えないといけないのではないかと思います。

佐藤 卓己氏
佐藤 その意味では、メディアリテラシー教育というのは教科として捉えるだけではなく、国語・社会・理科など、すべての教科において、リテラシーを持つべきだという意識が必要だと思います。現在のメディアリテラシー教育が、問題だと思うのもそのような理由です。
しかし、実際の初等中等教育で、「正解がない」と強く教えることが、社会一般で理解されるかについては、私はやや悲観的です。おそらく教える側の教員にとっても相当な負担で、その実践が可能な余裕ある教員は、ごく少数のような気が私はします。
実際の教育現場で起きている問題点とその可能性
坂本 例えば文科省の政策では、探究学習をやらなくてはいけないし、インターネットを使った探究学習もやらなくてはいけない。GIGAスクール構想政策によって、実際にやらせています。ESDでも行います。
ところが子どもたちは、オンライン情報を評価する能力がゼロに等しいのです。私は実際にユネスコスクールの授業を見学しました。先生は子どもたちにタブレット端末を用いて調べさせます。しかし、子どもたちはネットの嘘か本当か分からないような情報を集めてそのまま発表してしまうのです。それに対して先生は何も指導しません。さすがに大学ではこんなことはあり得ません。
情報源も評価しないまま発表させてしまい、それが探究学習と言われている。指導要領も「オンライン情報を評価する」という発想は希薄です。今までの伝統的な教育ではオンライン情報を扱ってこなかったからです。突然やってきたGIGAスクール構想で、オンライン情報を実際に評価しなくてはならない現状があるのだから、何とかしないと危険だと思います。
山脇 今、私たちは教師の方々向けに、メディアリテラシーの教え方を研修するようなプログラムを作れないか、とも考えています。「答えがないなら最初から何も教えなければいい」ということになりかねない中、ある種のモデルが必要だと考えています。
カナダでは先生がメディアリテラシーを教える資格を取るために、初級でも125時間の研修をします。日本では何をどうしたら良いか分からない中で、そうした研修があれば、先生方も助かるのではないでしょうか。
坂本 メディアリテラシーをめぐる学習指導要領がない状況なので、矛盾だらけです。コンピューターはあるけれど、どう使っていいのか分からないという状態です。だから、今までの伝統的なやり方で、まさに教える道具としてコンピューターを使うという発想に陥りがちです。
先生方の中では二極化しているのではないでしょうか。「一生懸命いろんなことを考えて使いましょう」と、「いや、めんどくさいから使わないほうがいい」と、完全に分かれている状態だと思います。教育委員会もそうじゃないかと思います。
佐藤 それこそ藤村さんの書いた第1章で、10代の生徒と50代の教師の情報環境のギャップが指摘されていました。この状況で、50代の教員に、10代のネットでの情報行動の教育がそもそも可能かという点においても、かなり教員側に負担だろうなと思いました。
つまり、新聞や本を読んできたこれまでの生き方を、特に変えたいと思わない教員が、学生と同じようなスマホ環境を土俵に教育を行いましょうというのは、相当ハードルが高いだろうなと感じます。藤村さん、いかがでしょう。
藤村 そうでしょうね。どちらかと言うと、僕の書いていた時の問題意識は、私を含むシニアな人たちの情報リテラシー、あるいはメディアリテラシーのほうが硬直的だし、長時間テレビにだけ執着している状態がどれだけ害悪か、ということです。
若い人は、少なくとも情報機器の操作については問題ないので、あとは情報源をどう分類していくかというメタな行動についてのトレーニングです。それに対して、シニアの人の多くは、テレビの情報チャンネルにしがみついているわけなので、「情報源を問題にしましょう」みたいな議論がないわけです。
つまり、「日本テレビが言っていた」「NHKが言っていた」、いわば太鼓判付きの情報源から流れてくる情報をただがぶ飲みしているという状態です。
教育現場や若い人にだけ何かの課題感をぶつけていくのは、ゆがんでいるなと私は思ってしまいます。
佐藤 その関連では、ウクライナ戦争に対するロシア政府のフェイクニュースをロシア国民が信じていると報道される時に、「ロシアの多くの年配の人たちはテレビしか見ない」ということが新聞でもNHKなどの放送でも言われていて、一方で「ネットでアクセスしている若い人たちはフェイクに騙されていない」と言われますよね。
でも、こうした単純化した議論をあまりやってると、社会の分断を考える際にどうなのかなと思うのです。「テレビばっかり見ているからフェイクに気づかないんだ」という議論で果たしていいのだろうかと最近思っているところです。
メディアの形式と社会の合意形成のあり方
山脇 ロシアの国営テレビが、今回の戦争について放送している内容は、確かにプロパガンダです。
一方、日本の放送法第4条のように、政治的な公平性を謳うルールがある民主主義社会においては、視聴者は、一つの意見だけでなく、それに反対する意見が自然に耳に入ってくる面があります。

山脇 岳志
アメリカでは、1987年に、政治的な公平性や多様な視点の必要性を謳っていた「フェアネスドクトリン」が廃止されてしまい、左右の極端な意見がテレビやラジオで流れ続ける結果、分極化が加速した面があります。
だから、ロシア、日本、アメリカとそれぞれの状況やメディア環境は違っています。
ネットに押されているとはいえ、まだ影響力のあるテレビやラジオについて、日本の放送法第4条のような「公平性原則」があるほうが、視聴者は多様性のある意見に触れることができ、僕は好ましいと思っています。
それはある種の「介入主義」ではあるのですが、人間は、プロパガンダ放送などで、一方向の情報を与えられれば、極端な方向に走りがちだという「歴史の教訓」でもあると思います。
国が放送をコントロールして、国にとって都合が良い内容しか流さないような全体主義国家はもちろん問題ですが、一方で、放送に対して、政治的な公平性、意見の多様性の確保のルールを定めるような規制がないと、社会的な分断はどんどん広がっていくのではないか、と思っています。
佐藤 私はメディア史が専門ですが、メディアはまず広告媒体・宣伝媒体として考えるべきだと思っています。メディアが宣伝媒体・広告媒体という時には、それは合意形成の手段だと思っていて、社会的な合意をどう形成するのかということが、究極的にはコミュニケーションの目的だろうと考えます。
現状ではバラバラに細分化されたメディア環境でセグメント化されていくわけですから、同じ知識を全く持たない、つまり共通の会話が成り立たない社会になっていかざるを得ない。それを回避するためには、まさにプラットフォームとしてみんながアクセスしているような「大きなメディア」というのが、社会には必要だろうと思っています。
「ロシアのテレビが悪い」という議論、それは「ロシアの国営テレビのコンテンツがちゃんと公正に作られていないから悪い」という意味だと思いますが、一般的なメッセージとしては「テレビばっかり見ているからああなるんだ」という印象であり、テレビの内容ではなくて、形式の批判になっています。しかし、多くの国民がアクセスするプラットフォーム的メディア、つまり「マスメディア」の形式に対する批判というのは、あまりいい結果をもたらさないのかもしれないと思います。
新しいメディアリテラシーの見方
藤村 最近読んだダニエル・カーネマンの『ファスト&スロー』(早川書房)では、人間の認知システムを「システム1」「システム2」とに分けて説明します。前者は判断を高速に行い膨大な事象をおおむね問題なく処理しています。しかし、それは過去の経験や思い込みに頼っており複雑な判断やバイアスに弱い。一方、後者のシステム2は、精密な判断を行えるのですが、時間がかかりますし、並行処理が行えない。エネルギーも消費する。そのため、多くの判断はシステム1に委ねられてしまうというわけです。人間が高度な判断を行うための認知資源は有限で、すべてにじっくり時間をかけて意思決定していくのは無理、認知資源をあまり消費せず高速な処理ができるシステム1に多くの判断を委ねてしまっているという説明でした。

藤村 厚夫
今、インターネットの時代では情報が膨大です。それらすべてに対して冷静に時間をかけて吟味しなければならないというのは大変高度な要求です。限られた認知資源では十分な判断ができないという点に、大きな課題があると思います。
とすると、次の一手は、佐藤さんがおっしゃったように、リップマンの言うパブリックオピニオンを形成する人々を私たちが作り出していけるのか、あるいはそれに代わる仕組みを考え得るのかということが次の大きな課題だと思っています。
集合知的なものにその役割を期待してきた私たちIT関係者の楽観的な構想は、現在は相当に棄損している状況で、新たな模索の時期に直面しているなと思っています。
山脇 佐藤さんに伺いたいのですが、メディア論の父とも言われるマーシャル・マクルーハンは、メディアが伝える内容よりも、メディアの形式によって人間は影響されると言いました。分かりやすく言えば、テレビに慣れていたら「テレビ脳」、新聞に慣れていたら「新聞脳」になる側面があるわけです。
その意味で、ネットやスマホの衝撃は大きいと思うのですが、マクルーハン的に考えると、今の時代のスマホという形式における人間のあり方、影響をどう見ておられますか?
佐藤 現在、スマホで新聞を読む人やスマホでテレビを見ている人も多いわけです。彼らにとってのテレビというのはスマホで見るものかもしれない。その意味では、形式がマルチに統合されているというのがインターネットで、そこに形式の新しさがおそらくあると思います。
ニューメディアのニューメディアたるゆえんというのは、まさにそういうところで、スマホやタブレット一つあればラジオを聴くこともテレビを見ることも新聞や書物を読むこともできる。大概のメディアへのアクセスは開かれています。
そうすると、先ほどの「ロシア国民がフェイクを信じるのはテレビしか見ないからだ」というのは、「彼らがスマホを持っていないからだ」と翻訳されるわけであり、そうした議論で果たしていいのかということですよね。
山脇 たぶん今の若いユーザーにとっては、スマホでテレビを見ているという意識すらないかもしれません。逆に、YouTubeはスマホの画面でも見られるし、テレビ画面に映すこともできる。つまり、もうテレビを見るとかラジオを聴くとかいうことが、崩壊しているのではないでしょうか。
佐藤 そこまでの「デジタルネイティブ」と言われる人たちが、どの程度の割合で社会にいるのかという点も、私はやや疑問に感じています。もう一つ言えば、テレビは全世代にアクセスできるメディアとして登場したけれども、少なくともスマホは70代、80代の多くが今もアクセスできていないメディアです。
その意味で、藤村さんが書かれた10代生徒と50代教師のギャップというのは、テレビがニューメディアだった時代にはなかったことかもしれないということですよね。それが新しい局面だと思います。
坂本 「分断」と言われつつ、分断しているのは一部であり、マスメディアが分断を報じると、大部分が分断されているかのように受け止める問題もあると思います。いわゆるテレビ、ラジオのような伝統的なマスメディアとソーシャルメディアは、共犯関係のように分担して何らかの働きをしていると思うのです。
「ファシスト的公共性」に非常に関心を持ったのも、伝統的なメディアが1930年代のファシズムを作ったと言えるとしたら、今、新しいハイパーファシズムのかたちが、国境を超えたかたちでソーシャルメディア上で作り出されつつあり、それがたまたま陰謀論や分断というかたちで現れているのではないかという印象を持つのです。現在はソーシャルメディアがテレビと同じような機能を違うかたちで担っているのではないかと。

坂本 旬氏
人々が、どのようにして陰謀論を信じるのかと言えば、「自分に与えられたメッセージなんだ」と思った時に、その世界観に入ってしまう。1対1の拡散が非常に早いスピードで世界的に起こり、それを信じてしまう。だから、ロシアの問題もQアノンの問題も、国境を超えて進行しているのです。これをどう考えたらいいのかは非常に難しい。現在進行している話なので簡単には言えないのですが、メディアリテラシーについては、実はそこが一番のポイントです。
メディアリテラシーとは、本当は、情報の真偽ではなく、感情に働きかけるメッセージ性を見極めることだということ、その本質に改めて立ち戻って考えなくてはならないと僕は思います。
どう感情を作り出しているのか。特にルネ・ホッブスがメディアリテラシーの立場からプロパガンダという概念を新しくよみがえらせ(彼女は「現代的プロパガンダ」という言い方をしているのですが)、プロパガンダにはいいものも悪いものも両方あると言っています。
私たちは個別にプロパガンダを作り出しているし、発信もしている。それを前提に、新しいメディアリテラシーの見方もしなくてはならない時代に来ていると思います。
山脇 充実した議論をありがとうございました。
第2部 メディアの信頼性をどう考えるか はこちら