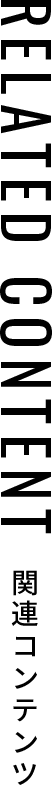 RELATED CONTENT関連コンテンツ
RELATED CONTENT関連コンテンツ





佐藤卓己氏(京都大学教授)による『メディアリテラシー 吟味思考(クリティカルシンキング)を育む』の書評を起点に、佐藤氏、坂本旬氏(法政大学教授)、山脇岳志(スマートニュース メディア研究所 所長)の3人が、メディアリテラシー教育の課題、そして、現代のメディアをめぐる可能性と問題点などを、歴史的観点も交えながら今後に向けて語り合いました。モデレーターは、同書の第1章を執筆した藤村厚夫(スマートニュース メディア研究所 フェロー)が務めました。全3回に分けて、お伝えしている議論の第2部。※第1部はこちら (以下、敬称略)
<登壇者略歴>
佐藤 卓己
京都大学大学院教育学研究科教授、副研究科長
1960年広島市生まれ、89年京都大学大学院博士課程単位取得退学。東京大学新聞研究所助手、同志社大学文学部助教授、国際日本文化研究センター助教授などを経て、現職。京都大学理事補、京都大学総長首席学事補佐兼務。著書に、『現代メディア史』(岩波書店)、『「キング」の時代』(岩波書店、日本出版学会賞受賞、サントリー学芸賞受賞)、『流言のメディア史』(岩波新書)など多数。
坂本旬
法政大学キャリアデザイン学部教授
1959年大阪府出身。東京都立大学大学院教育学専攻博士課程単位取得退学。専門はメディア情報教育学、図書館情報学。96年より法政大学教員。ユネスコ・メディア情報リテラシーと異文化間対話大学ネットワーク担当。アジア太平洋メディア情報リテラシー教育センターおよび福島ESDコンソーシアム代表。著書に、「メディア情報教育学」(法政大学出版局)、「メディアリテラシーを学ぶ」(大月出版)等多数。
山脇岳志
スマートニュース メディア研究所 所長
1964年兵庫県出身。京都大学法学部卒、朝日新聞社入社。経済部、調査報道担当、オックスフォード大学客員研究員、ワシントン特派員、論説委員、GLOBE編集長、ベルリン自由大上席研究員、アメリカ総局長、編集委員などを経て退職。スマートニュース メディア研究所 研究主幹に。2022年4月より現職。京都大学経営管理大学院特命教授を兼務。編著に『現代アメリカ政治とメディア』(東洋経済新報社)など多数。
藤村厚夫
スマートニュース株式会社フェロー/スマートニュース メディア研究所 フェロー
1990年代を株式会社アスキーで書籍および雑誌編集者、その後ロータス株式会社(現・日本IBM)でマーケティング責任者として過ごす。
2000年に株式会社アットマーク・アイティを創業。2005年に合併でアイティメディア株式会社代表取締役会長。11年同社退任。以後、新たなメディア産業のあり方をめぐる模索を開始。13年にスマートニュース株式会社執行役員。18年より同社フェロー。22年同社メディア研究所フェロー。
藤村 佐藤さんが第1部の議論の中でおっしゃったように、世論形成の過程で専門家によるパブリックオピニオンは必要ではないか。私は、集合知を比較的信頼するかたちで、今までのインターネットの発展を見てきたわけですが、それはかなり行き詰まりを見せていると思います。
佐藤さんのメディア史的な観点からすると、そもそもマスメディアは、大衆宣伝(プロパガンダ)のために発展した側面があります。それをどう多様化していくことができるのか、皆さんで一緒に考えていきたいと思います。
坂本 議論の冒頭で、情報の真偽ではなく、情報源の信頼性が重要であるという話をしました。アメリカではメディアリテラシーの授業で活用する教材の一つとして、「メディア・バイアス・チャート」というものがあります。第三者機関が公正な手続きによってメディアを評価して作られたチャートです。レフトとライトという政治性を横軸に、信頼性を縦軸にしたものです。アメリカでは、そのような情報源の信頼性を評価するチャートを作る第三者機関があり、それが一つの基準となっています。
日本にはそういった組織がないので、個人に任されていますが、「情報の真偽」そのものではなく、「情報源の信頼性」を評価するということであれば、さほど難しいことではないのです。先ほどのようなチャート以外にもあります。例えば、国境なき記者団が始めている新しいプロジェクトも客観的な評価によって、信頼性の高いメディアを認証する仕組みを試みています。
授業では、子どもたちに「情報源の社会的評判・評価を調べましょう」と伝えます。そのように情報源の信頼性を評価することは、実は情報の真偽ではなくて、ジャーナリズムの質を評価することにつながっています。
ソーシャルメディアがこれだけ普及している時代だからこそ、実はジャーナリズムの重要性、質の高さが重要だということを非常に強調しなくてはいけないと思います。特に今は戦争をめぐる偽情報が飛び交っており、どの情報を信じたらいいのかを考えることは重要なポイントではないかと思います。

ファシスト的公共性=佐藤卓己著(岩波書店)
そこで、佐藤さんにぜひお聞きしたかったことがあります。2018年に書かれた『ファシスト的公共性――総力戦体制のメディア学』(岩波書店)の中で、赤神良譲の「電体主義」に言及しています。ラジオは個人にメッセージを届ける手段として機能し、それがいわばファシズムを担っていったという話でしたが、まさに同じことが今も起きているのでしょうか。
特にロシアに関して言うと、ノーベル文学賞作家のスヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチさんがETVで「今ロシアで起こっているのはファシズムの兆候だ」とおっしゃっていました。本当にそう言えるのか。そして、今はラジオやテレビではなくてソーシャルメディアの時代です。同じように「電体主義」なるものがあるのかどうか、意見を聞かせてもらえればと思います。そして、そういう状況の中で僕たちはどうすればいいのかということがとても大事ではないかと思っています。
佐藤 「電体主義」についてまずお答えします。社会学者・赤神良譲の「電体主義」とは1940年という戦時下に唱えていた国民的合意形成の理論です。個人と国民を融合する「電体」は、電気でつながっているシステム社会の理念ですね。かつて読書する個人は、ランプの下で本を読むという、いわゆるスタンドアローンの光で読んでいました。この市民社会から進化して、都市全体を照らすシステムとしての光の中で本を読む大衆社会になる。赤神は個人主義と全体主義を止揚する新しい日本主義として「電体主義」を唱えました。その中で人々が情報を取り入れ、意識を作っていく。これ自体は、こんにちのインターネットに重ねてイメージしやすいものだと思います。今日の社会システム論の起点の一つとして「電体主義」を取り上げました。
坂本さんがおっしゃる「情報の真偽ではなくて情報源の信頼度」という点には、私も同意します。ただ、実際のメディアリテラシー教育の現場では、そうは言われてないのではないかという懸念があります。「メディアの発信する情報を疑いましょう」というところに、力点が置かれてきた印象を個人的に持っています。逆に「このメディアは信用できます」ということを、積極的に伝えるメディアリテラシー教育が、果たして現場で行われていたのか疑問に思うところです。
例えばリップマンは「完璧な市民というのを想定できないから専門家に任せるところは任せましょう」という議論を『世論』ではっきりと書いていますが、日本ではリップマンの主張としてほとんど紹介されない部分ですね。むろん、教室で「朝日新聞は信頼できるメディアです」「NHKは……」と言うことはないでしょうし、メディアがそう自己主張したとしても今の社会では「上から目線だ」とか、批判されると思います。
メディアリテラシー「教育」の一番強いメッセージというのは「メディアの情報は疑いましょう」というところにあり、その中で果たして「信用しましょう」「この情報源は信頼できます」ということを誰が強く言えるのか。それは非常に気になっているところです。

坂本 旬氏
坂本 実は、情報源の信頼性の話はメディアリテラシーの文脈から出てきたのではなく、スタンフォード大学歴史教育グループが開発した手法です。彼らは自分たちのリテラシーを「デジタルリテラシー」と呼ぶこともあります。少なくともメディアリテラシーとは呼んでいない。今は、さまざまなリテラシーの考え方が出てきていており、多様だと思います。
先ほどのジャーナリズムの話で言うと、ニュースリテラシーがその立場ですよね。メディアの質、信頼性を守りたいというジャーナリストの視点と関係が深いと思います。ですから、今は、一概にメディアリテラシーとは言えないほど多様なリテラシーが必要になっているのではないでしょうか。
佐藤さんが書かれた『ファシスト的公共性』の序文で「弾丸理論(マスコミの影響力を爆弾の破壊力のように強大だ、といった理論)」の話が出てきますが、メディアリテラシーを弾丸理論のように受け取られ、メディアリテラシーは「メディア批判」だと理解されがちですが、本当はそうではありません。
本来、メディアリテラシーは、「メディアメッセージの意味は、受け手側が主体的に構成する」という発想が土台になっています。欧米のメディアリテラシー研究者も、メディアリテラシーはメディアバッシングではないと言っています。日本でのメディアリテラシーの理解とはズレがあると思います。
佐藤 先ほどのロシアはすでにファシズムなのか、ということに関連しますが、「ポスト・トゥルースの時代」という状況に対して私はあまり不安を感じていない。むしろ「トゥルースの時代」こそがファシズムの時代だと思っています。
今のロシアにおける「フェイクニュースを伝えると懲役15年」という類の法律は、ソビエト共産主義の時代、ナチ第三帝国、戦前軍国主義の日本でもあったように、「これが真実だ」と国家が認定しないものは語ってはならないという言論統制の状況です。そのほうが、流言蜚語があふれるポスト・トゥルースよりもはるかに恐怖社会であることをまず前提に考えなければいけないと、私は思っています。
インターネットを基盤とした社会でも中国やロシアの状況を見れば「トゥルースの時代」は作ろうと思えば作れます。
多様な意見が存在すること、間違ったものも含めてあいまいな情報があふれている状況そのものを、ネガティブに捉えすぎないほうが良いと思います。まずは受け手の「耐性」の問題として捉え、間違っているものに過敏にならない・聞き流すという思考があれば多くの場合は済むのです。
その意味で言えば、インターネット社会がファシズムに近づいているかどうかの問いではなく、ネットをどう使うかによってどう変わってくるのかが重要だと、個人的には思います。
山脇 先ほど佐藤さんが「専門家を使うしかない」と話されました。私も『メディアリテラシー 吟味思考(クリティカルシンキング)を育む』の第16章(「虚実のあいまいさとメディアリテラシー」)の中に「ファクトチェックを人手やコストを掛けてきちんと行うメディアや、きっちりした専門家の意見を見分け、信頼していくことが、自らの時間の節約や精神の安定につながる」と書きました。
結局ファクトチェックもクリティカルシンキングも、やりだしたらきりがないのです。時間の制約を考えると、適当なところで切り上げるしかなく、新聞、メディア、専門家に対して、どの情報が信じられるのかある種の「勘」を持つということが重要だと思います。そして、「あいまいなもの」については放っておくことも必要です。
第1部で、佐藤さんから「ダイエットは成功しないからビジネスとして成り立っている」という話がありました。僕はそれでもダイエット産業に意味がないとは思っていません。僕自身、太り気味ではあり、いつもダイエットに苦労していますが、例えばダイエットのコマーシャルを見るだけで、「ダイエットしなくては」と思うわけです。実際には、十分にはダイエットに成功してないけれど、そういう情報なり警告がなければ、もっと太っている可能性も高いわけです。
ある種の建前だとしても、目標を持つのが大事ということはある。「刺激の強い情報ばかり摂取していたら、不健康になっていく」と誰かが言ったほうがいいと思うんですよね。その役割をメディアリテラシー教育は担うことができると思っています。
佐藤 その点は、そのとおりだと思います。『輿論と世論』(新潮選書)という本を書いた時に、それに対するかたちで、「佐藤の言う輿論というのは19世紀の市民社会にはあったものだけど、今の20世紀以後の大衆社会にパブリックオピニオンなんていうものは存在しえない。それは19世紀の特権的なブルジョワジーの中であり得た、それもあり得たかもしれない理想型に過ぎない」という批評がありました。実は、それはある部分、正しいと思っています。
今あるのはパブリックオピニオンではなく、「ポピュラーオピニオン」か、あるいは「パブリックセンチメンツ」かの2つしかなくて、その意味では、輿論というパブリックオピニオンの復興を唱えること自体が反時代的かもしれないとは、実は私自身も思っています。

佐藤 卓己氏
ただ一方、輿論のような規範がなければ世論の現状を批判する足場がないというのも事実です。その意味で、メディアリテラシーの、あるいは「吟味思考」という理想がなければ、なし崩し的に情報に接してしまうという議論はよく分かるのです。
ただ、メディアリテラシーの問題とメディアリテラシー「教育」の問題も、やや違った側面があると思っています。「教育」というかたちにすると、すべての生徒に伝えなければならない標準的なものになってしまうわけです。その時に、問いを簡単なものにする、あるいは、みんなが乗り越えられる水準のレベルに、目標値が下げられるということを、危惧しています。
先ほど坂本さんが、「実際のメディアリテラシーでは真偽が分からないということは常識なんだけど、でも、現場ではそうなっていません」と言われましたが、やはり真偽が判定不可能だということを認めたうえで教育するということが、現実には難しいからなのではないかと私は思うのですけれども、坂本さん、どうなんでしょう。
坂本 それは非常に興味深い質問です。メディアリテラシーがすべての生徒が学習する制度になった時、もともとメディアリテラシーが持っているラジカルな部分がどうなるのかという問いだとも言えます。つまり、メディアリテラシーは脱構造主義的なものを持っていますが、制度化されてしまうとどうなるのか。
イギリスでメディアリテラシー教育が制度化された時、レン・マスターマンという研究者が「メディアリテラシーはトロイの木馬だ」と言いました。つまり、制度化されてメディアリテラシーが授業の中に入ると中身はどんどん薄くなる。ところが、理論そのものがラジカルであれば、実践では人間がやるので、ラジカルな実践ができると言い、そのことを「トロイの木馬だ」と言ったのです。
制度化と実践は、分けて考えないと制度に取り込まれてしまうと思います。特に学校制度は国がコントロールする制度なので、つねに国の都合のいいようにコントロールされる可能性があります。
カナダのメディアリテラシー教育もそうです。保守政権になると、メディアリテラシーのいい部分はどんどん崩されてしまう。しかしそれは制度の問題であって、実践や理論の問題は、きちんとラジカルさを失わないようにするべきだと多くのメディアリテラシー研究者は思っているし、僕もそう思います。その辺は常に矛盾があるのだと思います。
もう一つぜひここで僕が思っていることをお話ししたいと思います。佐藤さんがおっしゃった、ファシスト的公共性の話に関心を持っています。今の社会的に話題になっている陰謀論ですが、ロシアのプロパガンダは「ロシアは正しい戦争をしている。正しいことをやっている。ナチスと戦っているんだ」というストーリーを描き、多くのロシア人はそれを信じてしまっているとされます。外から見ると「何を考えているのだ」と思うかもしれないけれども、実は同じことを言っている日本人が思いの外たくさんいるのです。
ソーシャルメディア上では、ロシアのプロパガンダをそのまま拡散している人がいっぱいいて、その人たちはいったいどういう人なのだろうと調べてみたのです。そうすると、その人たちは、「Qアノン」を信じている人たちでした。陰謀論を信じるグループは日本にも多い。その人たちはロシアのプロパガンダも受け入れてしまう。
陰謀論をなぜ信じるのかと言えば、陰謀論には世界観があるのですね。その世界観を信じてしまうと、世界は違って見える。そこに新しい真実があるかのように思ってしまう。
それはまさに、先ほどの赤神良譲の「電体」のようなものだと思うのです。ラジオが個人にメッセージを送って新しい世界観を伝えるかのごとく、今のソーシャルメディアの時代は、メッセージを受け取った人がそれを自分の世界観として受け入れる。その途端、世界が変わってしまう。そういうことが今、急速に拡散し、分断につながっていると思うのです。
ということは、ファシスト的公共性の概念をもう一回捉え直さなければいけない、今の時代の中でどう考えるのかということがとても重要なのではないかと思うのです。ぜひ佐藤さんの意見をうかがいたいと思います。
佐藤 私はこの書評の中でも、ハーバーマスの市民的公共性の議論を批判するかたちで書いています。日本では「市民的公共性」と訳されていますが、原語の直訳なら「ブルジョワ的公共性」で、それと対になるのがファシスト的公共性なわけです。
ブルジョワ的公共性の「ブルジョワ」というのは、財産と教養のある知的なエリートです。その人たちによって担われる公共性であり、そこから生まれる輿論である以上、「輿論は19世紀のエリート的な意見だ」という批判を当然受けざるを得ないと思います。
一方、ファシスト的公共性というのは、それはまさにナチ運動がそうであるように、街頭に出て「ハイルヒトラー」と叫ぶということで、政治への参加感が満たされる空間です。つまり、参加のレベルを極端に低く下げる公共圏ですね。つまり、拍手喝采するだけで、考える必要はない、「〇〇万歳」でも「打倒××」でも何でもいいから皆で叫ぶだけで参加感覚が得られる空間というのが、ファシスト的公共性だろうと思うのです。
その意味で言えば、まさに陰謀論も理屈ではないのです。陰謀論のツイートにリツイートする、あるいはFacebookでそれに「いいね」のボタンを押すという、共感の動員で参加感覚を生み出すシステムの中で、敵味方が分かりやすい陰謀論を軸にファシスト的な公共性が駆動しやすくなっていることは間違いない。
さらに言えば、『ファシスト的公共性』にも書いていますが、多くの人が参加感覚を得ることができるかどうかが民主主義の基本的な条件だろうと思うのです。少なくとも大衆社会における民主主義では、有権者、あるいは社会の構成員が「自分はこの社会に参加している」と思えるかどうかが重要です。
実際、ナチ第三帝国のドイツ国民は、まさに拍手喝采をする中で参加感を満喫していたし、今のロシアにしてもウクライナにしても、戦時下の社会は基本的には社会が一つの方向に向かって動いているから、参加感の高い社会になっています。私はそれを「戦争民主主義」と呼びます。だから、民主主義を「参加感覚」のレベルで捉えるのであれば、現在のロシアもおそらく民主的です。ロシアで「Z」のTシャツを着て街を歩く人がたくさんいるというのも納得します。
その文脈で言えば、メディアリテラシー教育で容易に真偽が分けられるというイメージが与えられると、生徒の参加感覚を高めるには有効だとしても、陰謀論への参加も促す危険性があると感じるわけです。

山脇 岳志
山脇 重要な論点だと思います。坂本さんも本の中で、「メディアリテラシーはメディア批判ではない」「真偽は見分けられない」ということを書かれておられますが、残念ながら、一般的なメディアリテラシーのイメージは違う。
しかも、学校教育に落とし込んだ時に、それが簡単なものになり、目標値が下げられ、あまり意味がない、あるいは、むしろ有害なものになってしまいかねないという佐藤さんの懸念は、私も十分理解できます。
授業実践例として本の中でも紹介していますが、私たちの研究所では、擬似SNS上で情報の真偽を判断してもらい、拡散するかどうかの判断をしてもらうシミュレーションゲームを開発し、中学校〜大学で実践しています。その授業の中では、「真偽を見極める」ということではなくて、「実際は見極められない情報も多い」ということを教えています。
投稿のシェアを広げていくことの是非も含めて考えてもらうゲームなのですが、よく分からない情報については、「シェアする前に、いったん立ち止まって考えましょう」と伝えています。まさに佐藤さんのおっしゃる「耐性思考」を教えているようなところがあります。
このゲームは、すでに1万人以上の学生などが使っていますが、参加者の満足度が非常に高いんです。アンケートで90パーセント以上が「非常に良かった」と回答しています。
こういったゲームを使い、「実は真偽が分からないことが多い」「あいまいなことが多い」ということを説明すると、教育委員会関係者や学校の先生方の中には戸惑う人もいます。
正確に言えば、大きく2つに分かれると言えそうです。「こうした手法こそ必要だ」という方も多くおられます。一方で、これまでやってきた教育とあまりにも違うから「対応できない」というような方もおられます。
ただ、少なくとも、私たちは目標値を下げたり、「白黒」をつけるような、簡単なものにしたりはしていません。
学校の教育現場では、先生が生徒に正解を教える方式の授業は、まだまだ多い。
しかし、世の中には、正解がない問いはたくさんある。「マル」「バツ」がつけられないものも多い。
もちろん知識を教えることを放棄してほしいという意味ではありません。一定程度は知識を伝えることは重要ですが、根っこの部分では、先生自身も「分からないことが多い」ということを認め、生徒とともにプロジェクトベースで、一緒に考えていくような教育に転換していくことが必要なのではないかと思います。「吟味」してもなお分からないことがあるから、一生、学び続けていく、考え続けることが重要だと思います。
メディアリテラシー教育には、そうした「態度」を育む力があると考えられ、こうし未来が見えにくい時代だからこそ、学校現場に広がってほしいと願っています。
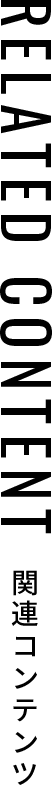 RELATED CONTENT関連コンテンツ
RELATED CONTENT関連コンテンツ



