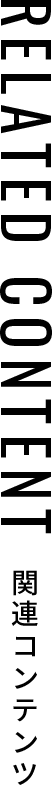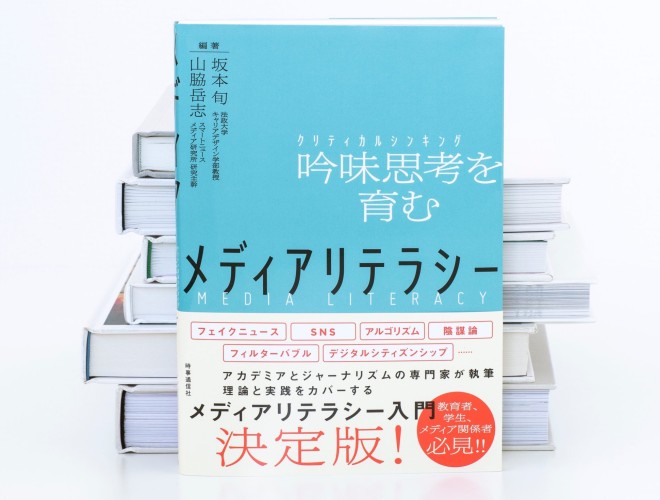佐藤卓己氏(京都大学教授)による『メディアリテラシー 吟味思考(クリティカルシンキング)を育む』の書評を起点に、佐藤氏、坂本旬氏(法政大学教授)、山脇岳志(スマートニュース メディア研究所 所長)の3人が、メディアリテラシー教育の課題、そして、現代のメディアをめぐる可能性と問題点などを、歴史的観点も交えながら今後に向けて語り合いました。モデレーターは、同書の第1章を執筆した藤村厚夫(スマートニュース メディア研究所 フェロー)が務めました。全3回に分けて、議論の内容をお伝えします。(以下、敬称略)
<登壇者略歴>
佐藤 卓己
京都大学大学院教育学研究科教授、副研究科長
1960年広島市生まれ、89年京都大学大学院博士課程単位取得退学。東京大学新聞研究所助手、同志社大学文学部助教授、国際日本文化研究センター助教授などを経て、現職。京都大学理事補、京都大学総長首席学事補佐兼務。著書に、『現代メディア史』(岩波書店)、『「キング」の時代』(岩波書店、日本出版学会賞受賞、サントリー学芸賞受賞)、『流言のメディア史』(岩波新書)など多数。
坂本旬
法政大学キャリアデザイン学部教授
1959年大阪府出身。東京都立大学大学院教育学専攻博士課程単位取得退学。専門はメディア情報教育学、図書館情報学。96年より法政大学教員。ユネスコ・メディア情報リテラシーと異文化間対話大学ネットワーク担当。アジア太平洋メディア情報リテラシー教育センターおよび福島ESDコンソーシアム代表。著書に、「メディア情報教育学」(法政大学出版局)、「メディアリテラシーを学ぶ」(大月出版)等多数。
山脇岳志
スマートニュース メディア研究所 所長
1964年兵庫県出身。京都大学法学部卒、朝日新聞社入社。経済部、調査報道担当、オックスフォード大学客員研究員、ワシントン特派員、論説委員、GLOBE編集長、ベルリン自由大上席研究員、アメリカ総局長、編集委員などを経て退職。スマートニュース メディア研究所 研究主幹に。2022年4月より現職。京都大学経営管理大学院特命教授を兼務。編著に『現代アメリカ政治とメディア』(東洋経済新報社)など多数。
藤村厚夫
スマートニュース株式会社フェロー/スマートニュース メディア研究所 フェロー
1990年代を株式会社アスキーで書籍および雑誌編集者、その後ロータス株式会社(現・日本IBM)でマーケティング責任者として過ごす。
2000年に株式会社アットマーク・アイティを創業。2005年に合併でアイティメディア株式会社代表取締役会長。11年同社退任。以後、新たなメディア産業のあり方をめぐる模索を開始。13年にスマートニュース株式会社執行役員。18年より同社フェロー。22年同社メディア研究所フェロー。
「吟味思考」と「耐性思考」の持つ共通性
藤村 時事通信社の時事ドットコムの「今月の一冊」に、『メディアリテラシー 吟味思考を育む』(以下『メディアリテラシー』)について、佐藤さんが大変丁寧な書評を寄せてくださいました。そこに含まれている問題意識を広げていくところからスタートしたいと思います。
『メディアリテラシー』の「吟味思考」というコンセプトに対して、佐藤さんは「耐性思考」という対抗軸・コンセプトを示されています。佐藤さんがお持ちになった問題意識から触れていただければと思います。

メディアリテラシー 吟味思考(クリティカルシンキング)を育む=坂本旬、山脇岳志 編著、時事通信社
佐藤 今、最も関心のあることは、分断社会についてです。情報社会の中、リテラシーによってギャップが生まれ、社会が分断されていく状況の深刻さを、ひしひしと感じています。
この本(『メディアリテラシー』)では、主にアメリカ社会におけるこれまでの実践が多く紹介されていますが、そのアメリカにおいて、トランプ大統領が登場し、極端な分断社会が出現している。メディアリテラシーは1980年代頃から続けられてきていますが、その活動が、現在のアメリカ社会にどのような意味を持ったのかを考えながら読みました。
例えば、メディアリテラシーがカナダで盛んに取り上げられた理由の一つは、アメリカのテレビや新聞の情報がスピルオーバー(放送対象地域外で受信できること)してカナダに入り、カナダの文化的統合を揺るがす危険性が出てきたという背景があったためです。その意味では、メディアリテラシーが社会の分断をどう防ぐかという問題意識と、出発点において不可分だったと思います。つまり、社会の合意形成に必要な能力として、メディアリテラシーが求められたことが重要なポイントです。
一方、実際のメディアリテラシー「教育」が、求められる理性的な合意形成に本当に役立っているのか、現実に目を向ける必要があるのではないか、というのが問題意識の出発点です。本書で紹介されているような、小学校や中学校の教育現場で情報を吟味するメソッドがそれなりの意味を持つことは十分理解していますが、そのうえで、この手法を用いたら情報の真偽が判定できると考えてしまうことの危険性にも不安を感じたのです。
私たちは分かりたがる脳を持った生き物で、分からないことになかなか耐えられない。メソッドがあると、そこにはめ込もうとする。解けない問題を解こうとした時に、問題そのものを単純化するかたちで処理してしまう危険性を、私たちは絶えず持っていると思うのです。
答えが出ない問題に私たちは耐えられないから、単純に答えが出る問題に書き換える。それが陰謀論や、単純な「敵か味方か」という白黒図式になるのかもしれない。そう考えると、歴史の中で、メディアリテラシーにどの程度の効果効用があったのかどうか、本来はその検証が最初に必要です。
ところが、このメソッドをメディアリテラシー「教育」に発展させると――「教育」とは基本的には性善説の立場に立ち、成長の可能性にかけるプロジェクトですね――、その善意を前提とするために教育効果の検証がされないのではないかという問題意識を持ちながら、この書評を書いたのです。
藤村 佐藤さんの書評では、「耐性思考」という言葉が非常にユニークに映りました。その言葉についても伺いたいと思います。正しい・正しくないを見極めることに意識の指向性が強まってしまうものに対して、スルーする力も併せ持とう、という意味にも受け止めました。

オンラインで行われた鼎談の様子
佐藤 例えば、治療しなくても時間が解決する、治ってしまう病気は、案外多い。「待つ」ということが本来は必要なのかもしれない。だけど、患者は自分の病気が知りたいし、早く治療されたい、処方されたいというのが、今の社会のありようだと思うのです。早く分かりたい、決断したいというファスト社会です。
私はクリティカルシンキングというのを、「吟味思考」と訳されたことは非常に意味があると思っています。クリティカル、つまり「批判」と言った時に、特に性急な批判であればきわめて有害なことになる。批判する時には時間をかけて批判をしなければいけない。その意味では、吟味と耐性という言葉には、どちらも時間の幅を持っていて、重なる部分はあると思うのです。
情報の真偽判定ではないメディアリテラシーの本来の意味
藤村 メディアリテラシーに「教育」というものを組み合わせた時に、考えるべき課題を佐藤さんから提示していただきました。坂本さんはどういうふうに考えますか?
坂本 メディアリテラシーが真偽を判定する能力と見なす危険性については、アメリカでも議論されました。ダナ・ボイドが2017年にメディアリテラシーの「バックファイヤー」について記事を書き、大論争になりました。トランプ氏が大統領に当選した直後の話ですが、理性を前面に出した「批判的思考」を主張するメディアリテラシーが、逆の効果をもたらしたのではないかという指摘です。それに対し、『メディアリテラシー』にも出てくるルネ・ホッブスが反論を行っています。メディアリテラシーを考えるうえで興味深い議論でした。
第3章(「メディアリテラシーの本質とは何か」)に書きましたが、メディアリテラシーは事実か事実でないかということを判断する能力ではありません。この章に「だいじかな」リストを入れているのですが、これはもともとメディアリテラシーの概念ではありません。情報リテラシーとして提示しているのですが、多くの人は「だいじかな」をメディアリテラシーと見なしてしまう。それは実は大きな間違いです。
もう一つ、「さぎしかな」という5つのキークエスチョンを載せているのですが、実はそれが一番大事なのです。そこを見抜いてくださったのは、今のところ、苫野一徳さん(熊本大学教育学部准教授)だけです。
「さぎしかな」がなぜ大事なのかといえば、これは答えが簡単に出てくるような質問ではなく、じっくり考えないといけないような問いだからです。一番大事なのは、自分の感情が動かされた時に、それはどんな表現技法によって感情が動かされたのか、あるいは、自分以外の視聴者がどのように受け止めたか、と考えなくてはいけない点です。だから、実はメディアリテラシーの基本があまり理解されてないと思っています
ただ、そうは言っても情報の真偽を判定する力が必要であることは間違いありません。そこで、本書の『メディアリテラシー』は、そのような考えも含めました。つまり、情報リテラシーもニュースリテラシーもデジタルリテラシーもすべて、広い意味でのメディアリテラシーと見なしましょうという提案です。メディアリテラシーとは何かというややこしい議論をしなくて済むようにすることが一つの眼目だったわけです。
このようにして、メディアリテラシーには、長くじっくりと考える部分もあれば、情報の真偽の部分もあると捉えています。ただ、教育の現場では、「情報の真偽を判定する」とは教えないのです。スタンフォード大学歴史教育グループが新しい「横読み」という方法を提案しています。横読みとは、情報の真偽の判断ではなく、情報源の評価をする。情報源の評価であり、「マル」か「バツ」かにはなりません。グラデーションがあるのです。そのために探究していかなければいけないのです。教育現場でも、その情報源へのプロセスをたどっていくことを、子どもたちがパソコンを使って学びます。
佐藤さんがおっしゃったように、実際のところ、どうしても真偽の判定という点に多くの人が関心を持ってしまいます。そのために、メディアリテラシーもそのような観点に引き寄せられ続けているのではないかと思います。
多様で多角的な視点を保つために必要なこと
藤村 山脇さんはジャーナリスティックな観点からも、メディアリテラシーについて考えられてきました。ロシアによるウクライナ侵攻のようなことがあると、情報の真偽で大論争になる。あるいは、それが世界を動かす課題になるようなところに、われわれは直面している。その世情の中で、メディアリテラシー、「吟味思考」ということを語ることの意味について、山脇さんの考えも伺いたいと思います。

藤村 厚夫
山脇 明らかなフェイクニュースや陰謀論についてはある程度の見極めはできますが、佐藤さんがおっしゃるように、見極められないことや、あいまいな部分は多いと思っています。そのあいまいさに対する「耐性思考」が重要だというご指摘については、賛成です。本の中でもう少し書き込めば良かった、あるいは佐藤さんにも1章分のご執筆を、お願いすれば良かったとも思います。坂本さんの章(第3章)で、デビッド・バッキンガムが「白と黒の間には大きなグレーゾーンがある」ということにも触れられていて、メディアリテラシーの学者はそのグレーゾーンの存在を分かっているわけです。
しかし、これだけフェイクニュースや偽情報が多いと、情報の真偽の区別が大きな話題にはなってきますよね。事実は光の当て方で見え方も違うし、事実もとらえ方によっては虚偽に近いこともあります。ある種の相対性を理解することは重要で、そのことを教えないといけない面もあるのではないかと考えています。
そもそも、学校の先生方のお話を伺うと、ソーシャルメディア(SNSより広い概念)を使われている方の割合が多くはないと感じます。YouTubeで一回、陰謀論的な動画をクリックしてしまうと、アルゴリズムによってどんどん似たような動画が出てきてしまう仕組みなどもご存じない先生も多いと聞きます。「アルゴリズム(の概念)とはこういうものです」「アルゴリズムによって、(自分の見たい情報しか見えなくなりがちな)フィルターバブルに陥りやすくなるリスクがあります」という「知識」を伝えるだけでも、大きな意味があるのではないかと思います。
佐藤さんからは、以前にも、アメリカのほうが日本よりもメディアリテラシー教育が進んでいるにもかかわらず、トランプのような人物が出てくること、分断が激しい、という指摘を受けたことがあります。つまり、メディアリテラシー教育が進んでいても、分断は緩和されないではないか、という疑問だと思います。その疑問はよく理解できます。
ただ、分断が生じている最も大きな理由は、格差の広がりや経済的な要因であり、それを解決しようとしない既得権益層・エリート層に対する強い不満というものがあると思います。特にオバマ政権の8年間、貧富の差は縮まらない中で、平等主義的であるはずの民主党政権にも見捨てられたと考える人たちも増えていた。その中で、トランプなら何かやってくれるのではないかと考える人たちが増えたのはやむを得ないことだったかもしれません。ほかにも、移民問題、人種差別、ジェンダー、LGBTなどをめぐる価値観の違いをどう考えるかといった点も分断を広げており、メディアリテラシー教育なりメディアリテラシーができることはある程度限られていると思います。
加えて、僕が以前に執筆した『現代アメリカ政治とメディア』(東洋経済新報社)にも書きましたが(第4章「揺らぐ報道の『公平性』」)、これだけアメリカにおいて分断が極端になった背景には、1987年に、放送事業者に対して公平性の担保を求めていたルール(フェアネスドクトリン)の廃止の影響もあると考えています。日本には放送法第4条が存在し、放送事業者には、なるべく政治的に公平になるように、多様な見方を示すことが求められています。アメリカにはそのようなルールがなくなってしまい、メディアを通じて、左右の極端な意見に晒され続ける結果、どんどん分極化が広がる原因の一つになっていると思います。
多様な立場、相手の立場に立って考える多角的な視点を持つことは重要だと思いますが、それがメディアに課されたルールとしては存在しないのだから、メディアリテラシー教育のほうの役割が高まってくる。メディアリテラシー教育は決して強力な武器ではないけれども、しかし、やって意味がないわけではないと思います。
ただし、効果が測定できていないのではないかという佐藤さんのご指摘は、重要です。
少しはあるんです。カリフォルニア大学のジョセフ・カーン教授の調査結果によれば、メディアリテラシー教育を受けていない若者は、政治的な知識が豊富であっても、事実を示されても不正確と認定しがちであることが分かっています。つまり、そうした若者はインテリであっても、もともとのバイアスに非常に影響されるのに対して、メディアリテラシー教育を受けた人はそうなっていないということが示されています。
これは一つ大きな材料だと思います。ただ、日本においてそういう効果が示されたものがありません。ですので、われわれは今、埼玉県戸田市と一緒に、その効果を測定・検証できないかという研究を始めようとしています。
アメリカにおいて、これだけ分断が進んでいるというのはもちろん良い兆候ではないのですが、しかし、それをもってメディアリテラシーが無力だとは言えないと思うのです。メディアリテラシー教育がなかったらもっとひどいことになっていたかもしれないということもあり得るわけです。そのあたり、佐藤さんのご意見も伺いたいと思います。
メディアリテラシーの現実的な出発点として
佐藤 私はメディアリテラシーという概念やメソッドが有効でないとは思わないのです。ただ、使いこなせる人が、どの程度社会の中に居るかという問題がさらに重要だと考えています。
例えば「吟味する」という営みを可能とするためには、ある程度の余裕がないといけない。これは時間的余裕でもあるし、生活の余裕でもある。そう考えると、それが社会の中の何パーセント、何割の人に要求することができるのかということは気になります。
例えばウォルター・リップマンが『世論』(岩波文庫・原著は1922年)で、「大半のアメリカのビジネスマンが一日に新聞を読むのは15分だ」と書いたのですが、15分であれば、見出ししか読まないですよね。あとは関心のある記事を何個か読む。そういった人に「吟味思考」が可能なのかどうか。一方で1日中メディアから流しっぱなしの情報を浴びている人、SNSでネットに1日中接触をしている人たちが個々の情報について吟味することがそもそも可能なのかどうか。それはまさにテクノロジー的な問題でもあります。

それに対して、「デジタルダイエット」という議論も紹介されていますが、ダイエットは多くの人が成功しないからビジネスとして成り立っています。それができるというのは、よほど意志が強くて、あるいはトレーナーが付いて、食事制限までちゃんと管理してくれる人が居てといった態勢が整っている場合に限られる。リップマンがまさに『幻の公衆』(柏書房・原著は1925年)の中で批判していることだけれども、完璧な市民というのを前提にした民主主義というのは危ない。われわれは完璧な市民ではないし、そういう能力をすべての人が持っていると仮定して社会的なモデルを構築するべきではないだろうとやはり私も思います。
リップマンは『世論』の中で、結局、真偽の判定は専門家を使うしかないと言っています。党派的に中立な専門家という存在を社会システムの中に組み込んで、多くの一般の人々は、どの専門家を信じるか、それを判断するしかないだろうと言っているのです。
私はメディアの役割は、本来そうした「専門家」の機能を果たすことだろうと思います。逆に言うと、そもそも新聞やテレビ番組の受け手に内容の真偽を判定しろということ自体が、メディアの役割を半分以上放棄していることになります。信用できるメディアを選ぶことしかできない人が圧倒的に多いという現実認識が、私はメディアリテラシーの出発点だと思っているところがあります。