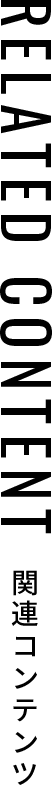第1回SMPP調査の見取り図(上)
スマートニュース・メディア価値観全国調査は、どう受け止められたのか?

日本に政治的・社会的な分断はあるのか。あるとすればどんな姿なのか。分断とメディア接触との関連はどうなっているのか。そうした点の探求を目的とした「スマートニュース・メディア価値観全国調査」が、2023年に開始され、もうすぐ2年となります。調査は10年計画で、2年ごとに行われ、第2回は来月(2025年1月)に実施されます。
第1回の調査結果は、日本政治学会、日本社会心理学会などの学会で発表されました。また、調査分析結果をまとめた書籍は、2024年10月、勁草書房から「日本の分断はどこにあるのか」というタイトルで出版されました。分析結果は、多くのメディアや研究者の方々に取り上げていただきました。ただ、調査で判明したことが多岐にわたるため「何がわかったのか、わかりやすく示してほしい」といった要望が寄せられることがあります。
そこで、本稿では、難しい事象をわかりやすく伝えるプロフェッショナルであるマスメディアが、どんな視点でこの調査を取り上げたかについてや、研究者の方々の論考の一覧などをお伝えすることで、第1回調査の全体像を「見えやすく」したいと思います。
第2回の実施を前に、第1回調査のいわば「見取り図」を示すことにもなろうかと思います。
 山脇岳志
山脇岳志
スマートニュース メディア研究所 所長
兵庫県出身。京都大学法学部卒。朝日新聞社で、経済部記者、論説委員、GLOBE編集長、編集委員などを務めた。アメリカには2回赴任(ワシントン特派員、アメリカ総局長)、欧州には、オックスフォード大学客員研究員、ベルリン自由大学上席研究員として滞在した。2020年、スマートニュース メディア研究所の研究主幹に就任、22年から所長。著書に「SNS時代のメディアリテラシー」(筑摩書房)など。編著・共著は「現代アメリカ政治とメディア」(東洋経済新報社)、「アメリカ政治の地殻変動 分極化の行方」(東大出版会)など多数。
調査を着想したきっかけ
まず、調査名が長いので、以下の表記はSMPP調査とさせてください。SMPP調査とは、SmartNews, Media, Politics, and Public Opinion Surveyの略称です。
こうした調査の構想は、2016年、筆者が朝日新聞社のアメリカ報道の責任者だった当時、トランプ氏が当選した大統領選を取材したこと、そしてピュー・リサーチセンターなどのアメリカの調査機関が早くからアメリカの分断状況を明らかにしていたのを知ったこと、その双方の体験から生まれたものです。
トランプ氏の当選は、アメリカ社会の分断の「原因というより結果」だといわれます。つまり、トランプ氏の言動がアメリカ社会を分断させる「原因」になったのではなく(分断を加速させたとは思いますが)、貧富の格差拡大、移民やグローバリゼーションなどを背景にした政治的・社会的分断の「結果」として、トランプ大統領が誕生したという意味です。今でこそ「通説」のようになっていますが、当初から自明ではなかったと思います。「結果」説が浸透してきたのは、トランプ氏が大統領候補になる以前から、ピュー・リサーチなどの客観的な世論調査などによって、すでに分断が示されていたという背景もあります。また、保守とリベラルといった有権者のイデオロギーの違いによって、マスメディアへの信頼度や接触しているメディアが全く異なることも、各種の調査によってわかっていました。
日本にも様々な優れた世論調査はあるのですが、ピュー・リサーチセンターの調査のように包括的な形で、政治的・社会的な価値観、メディア接触との関係がわかるものが、あまり見当たりませんでした。「日本版のピュー・リサーチセンター的な調査」を実現したいという思いは2016年ごろに抱き、信頼する同僚にも伝えていました。ただ、ピュー・リサーチセンターは160人以上の研究者・職員を抱える大きな調査機関です。長年のデータの蓄積やノウハウがあり、当時の私の願望は単なる「夢想」にすぎないものでした。それが、縁あって2020年にスマートニュースのシンクタンクに転職し、外部の優れた研究者の協力を得て研究会を立ち上げることで、「ピュー・リサーチセンター級」とまでは言えませんが、調査の構想が実現に向けて動き出しました。2023年春に第1回調査に漕ぎ着けるまで、着想から7年、具体的な準備を始めてからも2年以上を要しました。(実施機関、サンプル数なども含め、調査の概要は、こちらの研究所ウェブサイトにまとめています。)
研究会メンバーは、共同座長の池田謙一・同志社大学教授、前田幸男・東大教授を含め9人でした。包括的な分析を行うため、政治学、社会心理学、情報学など異なる分野の専門家に入っていただいたのが特徴です。
SMPP調査企画の理由・背景についての詳細は、「日本の分断はどこにあるのか」のまえがき、あとがきに記しています。(まえがきと序章の一部は、こちらの勁草書房のウェブサイトから無料で読むことができます)
各メディアからみた注目点
第1回調査の結果が出たのが2023年5月、そこから分析が行われ、8月から9月にかけて、日本政治学会や日本社会心理学会で、それぞれの専門分野について発表がなされました。学会発表によって、専門家の間ではある程度知られるようになったわけですが、調査の結果は一般の方々にも知っていただきたいと考えました。そこで、11月24日にシンポジウムを実施しました。その概要や、当日配布資料(86ページ)は、以下の弊社のウェブサイトから無料でダウンロードできます。
シンポジウムにはメディア関係者約40人のご参加をいただき、研究会側からの説明と質疑応答含め、約2時間にわたって開催されました。
このあと報道が相次ぎますが、調査結果の注目点は、(当然のことですが)メディアによって異なっていました。
まず、当日夜、配信された時事通信社の記事では「新聞やテレビへの信頼度は、米国では民主、共和党支持者間で大きな差があるが、日本では保守、リベラル層も7割程度が信頼しほとんど差がなかった」という点が触れられていました。
読売新聞は、翌25日朝刊の2面と4面を使って報道。2面は、日本ではアメリカに比べ、新聞やテレビといったマスメディアの信頼度が高いことや、保守・リベラル層で、メディア信頼度に差がないことが米国と違っている点などが取り上げられていました。
4面の見出しは、「好感度 岸田首相6位 メディア価値観全国調査 SNS利用層に不人気」となっていました。記事は、歴代9首相について、好感度が高い順に並べたわかりやすい表をつけ(トップは小泉純一郎氏)、岸田首相(当時)については高齢層ほど好感度が高く、SNSを中心に利用する層の好感度が低いことに着目していました。Yahooニュースにも配信されたこの記事は、数時間にわたってYahoo!トピックスの主要ニュースのトップ(一番上)になり、多くのインターネットユーザーにも読まれたようです。
「新聞・テレビ『信頼』68%…メディア価値観調査」(2023.11.25 読売新聞)
「歴代首相の好感度、岸田首相は9人中6位…SNS利用層に不人気」(2023.11.25 読売新聞)
朝日新聞は11月28日のデジタル版、29日の朝刊で報道。日米の比較を中心にした内容で、保守、リベラルの差について「米国の調査と比較した場合、いずれもイデオロギーによる差異は小さかった。特に経済面では、保守の方が増税や財政出動を求めるなど『大きな政府』を志向しており、米国と反対の結果が出た」と指摘しました。
「日本のリベラルと保守、米国とどう違う? メディアへの信頼度に差」(2023.11.28 朝日新聞)
日本経済新聞は、11月28日朝刊で、調査の概要について、「日本で保守とリベラルの政治的立場が鮮明になるのは安全保障や憲法問題」であり、「経済問題の保守かリベラルかの政治的な『分断』はさほどみられない」などと報じた後、12月8日夕刊2面「政界ZOOM」でSMPP調査の結果について詳しく触れました。また、研究会メンバーの遠藤晶久・早稲田大教授のインタビューを掲載、日本のイデオロギー対立の特殊性として、経済的な対立が非常に弱いこと、近年はジェンダーの対立が意識されていることなどのコメントを引き出しました。
「日本の『分断』は安保・憲法問題が軸 民間調査」(2023.11.27 日本経済新聞デジタル版)
「保守・リベラル、日米で差異 米国は同性婚で分断鮮明」(2023.12.8 日本経済新聞デジタル版)
Forbes JAPANは、オンライン記事で、マスメディアの信頼度が、年齢層によって違い、若い世代ほど低くなることに着目。情報源について、若い世代は友人やSNSを頼りにする傾向が見られることがわかったとし、「何か重要なニュースがあるときには、友達が教えてくれることをあてにしている」と回答した若年層が26%にのぼったことを指摘しています。
「メディア感度格差、データで顕在化! 若者にとっての『ネオ新聞一面』はこれ 」(2023.12.6 Forbes JAPAN)
研究会メンバーによる連載(ニューズウィーク日本版)
研究会メンバーも、分析結果をなるべくわかりやすく説明しようと務め、ニューズウィーク日本版に7回にわたって連載(2024年1月〜2月)が掲載されました。
ご関心のある分野があれば、ご参照いただければと思います(肩書きは執筆当時。連載記事の掲載順)。
「日本の『分断』を追う10年プロジェクト始動──第1回調査で垣間見えた日米の差異」
山脇岳志(スマートニュース メディア研究所長)
「首相への好悪から見る『分極化の起点』」
前田幸男(東京大学大学院情報学環教授)
「『イデオロギーの対立』は社会にどれくらい根付いているか?」
遠藤晶久(早稲田大学社会科学総合学術院教授)
「日本人の道徳的価値観と分断の萌芽」
笹原和俊(東京工業大学環境・社会理工学院准教授)
「メディア接触の新潮流...『ニュース回避傾向』が強い層の特徴とは?」
大森翔子(法政大学社会学部専任講師)
「『政治と関わりたくない人たち』がもたらす政治的帰結」
小林哲郎(早稲田大学政治経済学術院教授)
「統治の不安と分断がもたらす政治参加」
池田謙一(同志社大学社会学部メディア学科教授)
また、当研究所は、膨大な調査の中から、メディア関連のシンプルなデータを取り出し、「SMPP調査リポート」として、グラフを使った平易な解説記事を掲載しています。
SMPP調査レポート①:日本では、イデオロギー的傾向を超えて、マスメディアへの信頼度が高い
SMPP調査レポート②:浸透するSNS〜ネット利用者約8割がアカウント所持。一方で、全体の半数の人がSNS経由のニュースを「重要でない」と判断
SMPP調査レポート③:「ニュース回避傾向」のある人は全体の8% 回避傾向ある人の6割が「ニュースを楽しめていない」
ほかにも、SMPP調査についてメディア掲載・引用はありましたが、文字数の関係で、絞ってご紹介しました。
「SMPP調査の見取り図 (下)」では、書籍「日本の分断はどこにあるのか」からの引用や分析を中心にお伝えしたいと思います。