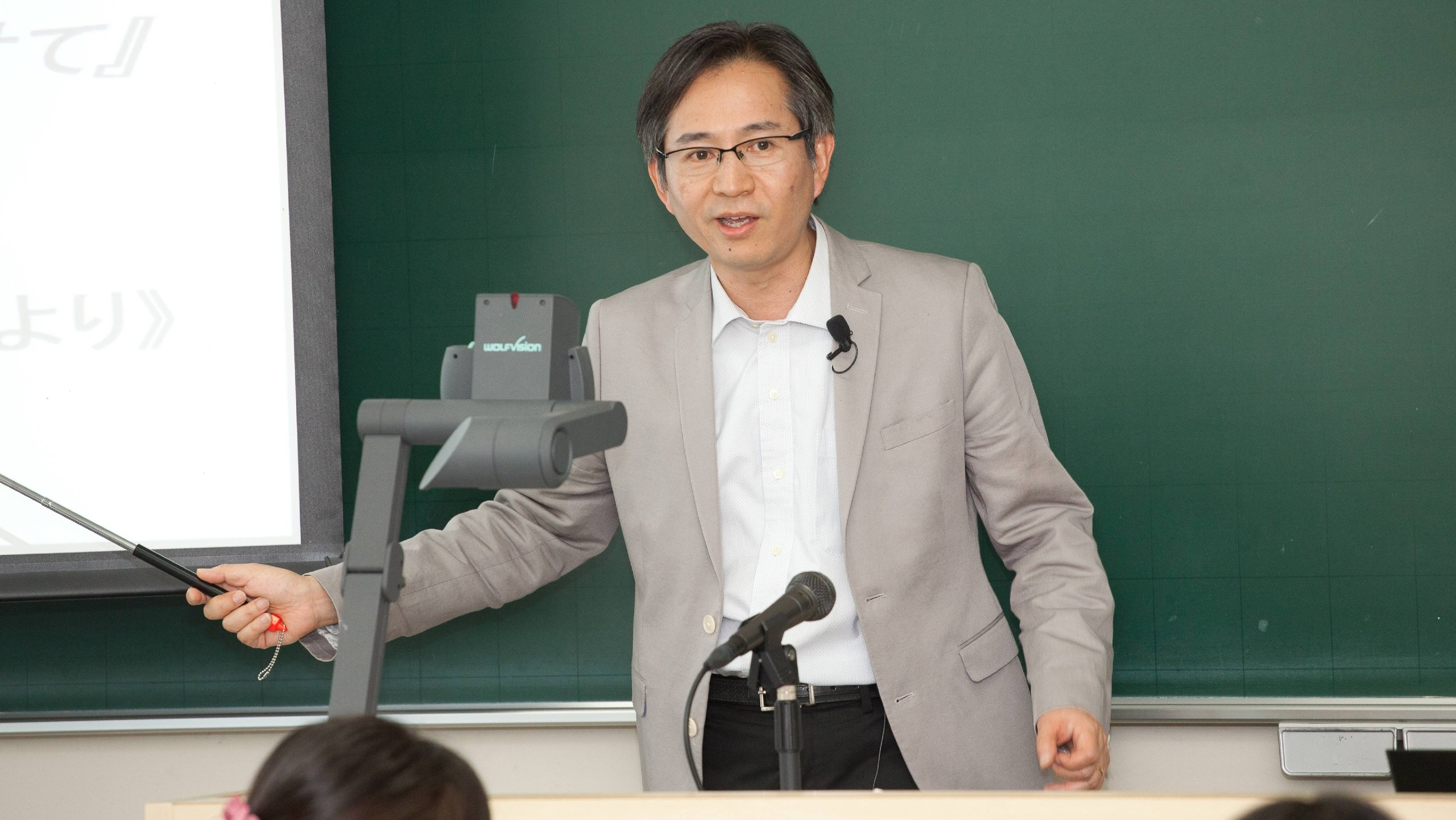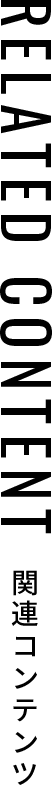日本の教育現場でメディアリテラシー教育の実践を重ねてきた下村健一氏のインタビュー。後編では、SNSが発達している現在における「発信する側」が気をつけるべきこと、さらに今後のリテラシー教育の方向性について聞いた。
下村 健一
令和メディア研究所 主宰・白鴎大学特任教授・JIMA(インターネットメディア協会)リテラシー部会担当
1960年生まれ。東京大学法学部政治コース卒。TBS報道局アナ、フリーキャスター計25年を経て、官邸にて内閣審議官等を2年半。慶應義塾大学特別招聘教授などを満了後、現職。光村図書の小学校5年の国語教科書に「想像力のスイッチを入れよう」を執筆している。これまで、小学校~大学、企業などで、数百回のメディアリテラシー授業を行ってきた。
発信者が注意すべき4つのポイント
――SNSが発達している今、いわゆるマスメディアだけがメディアなのではなく、すべての人が「メディア」になっているといえます。発信者の責任については、どう教えていますか。
4つのチェックポイントを示します。明確さと正確さ、優しさと易しさです。
まず最初に、明確さ。自分は何を伝えたいのかを、対面の会話以上にハッキリさせて発信しようということです。SNSは普段の会話と違って、相手がこちらの意を汲んでくれません。それぞれ自己流で解釈するので、曖昧な発信をするとあとで「そんなつもりで言ったんじゃありません」という釈明に大きなエネルギーを使うことになります。
2番目の正確さは、決めつけていないかです。自分の言葉足らずのせいで決めつけた表現になってしまい、伝え方で誤解を招く場合があるからです。発信に際しての表現のチェックです。
3番目は、優しさ。誰かを傷つけていないか、配慮すること。キメつけとキズつけは、1文字違いでどちらもすごく要注意です。誹謗中傷は、いまネットで最も深刻な問題の1つとして先鋭化されている部分です。軽い気持ちでやらかしていないか、気を付けようということです。
4番目は易しさです。「伝える」は発することで、「伝わる」は届くこと。専門用語の混入だけでなく、情報の受け手にとって必要な情報が整って伝「わ」っているかどうか、チェックしましょう。
この4つの発信者責任を具体的におさえないと、混乱が起きてしまうと教えます。
受信と発信は、コインの裏表です。いまは全員メディア時代なのだから、あなたには発信者責任もあります。発信は「メディアの人たち」が考えるべき問題だ、という旧来の発想は通用しません。
たとえば僕は、こんな例を出して説明します。「テレビのニュースが、渋谷の街で『コロナなんか怖くねえ』と騒いでいる若者を映すとき、外出を自粛してステイホームしている学生の姿は、そのカメラには映らないでしょう」それだけ言うと学生たちは、メディアには悪意の印象誘導があると考えがちです。そこで、すぐさまもう1つの例題を付け加えます。
「君たちが『あの角で家が燃えてる!』とLINEで友達に知らせるとき、『なお、他の角では燃えてません』と付け加えますか?」こう言った瞬間にみんな、「あっ、そうか。報道人だけでなく、自分も普段から情報を選択してるんだ」と気付きます。特異点だけを伝えていることがわかるのです。
――メディアには、異常な事態や非日常な出来事を取り上げる習性があります。
それがプロのメディア機関だけでなく、情報発信者なら個人であっても同じかもと思い至ってもらうことが重要なんです。
ニュースを教材に用いるなら、SNSや日常会話における情報交換の例もセットにして出すことで、「これは旧来のメディア固有の性質ではなくて、情報全般の性質なんだ。情報を伝えるとは、もともとそういう性質の行為なんだ」と気づかせ、それを踏まえた受信の心構えを持ってもらう。これはリテラシー教育においてとても重要で、授業を行なう人たちに気を付けてもらいたい部分です。
もちろん、時にはプロのメディア人が誤報や捏造を犯す事件はありますし、誇張や忖度が過ぎる報道があるのも確かです。けれど、それを以て一律に「メディアには気を付けろ」だけが強調された教育をしてしまうことは、情報キャッチボールの本質を見誤らせます。
授業で気を付けている点の最後は、ひとつの考え方に決めつけないことこそメディアリテラシーで身につけるべきポイントなのに、肝心の授業の進め方が決めつけになっていないか、ということです。何かの問いかけに対して、期待した答えを待ち構えてはいけません。それをやってしまうと生徒は先生の顔色をうかがって、模範解答を探してしまいます。
僕が各地の学校へ行って授業をするときも、子どもたちは「下村先生の求めている正解は何だろう」と猛烈に忖度して、授業の流れを外して恥をかかないように、と考えるわけです。
だから、まず宣言します。「先に約束する。みんなが何を答えても、僕は必ず『なるほど』と言うから、思ったことを何でも言ってみて」と。実際に彼らが何か答えたら、「なるほど、そういう見方ってあるよね」とうなずくのです。
広い視野を持とう、という授業で狭いひとつの答えを求めてしまったら、メディアリテラシーの授業ではなくなります。生徒が何を答えても「そうだね」と受け止めて、そこから授業を展開していくのです。
正解は、1つだけではない
――世代によって、教え方は変えていますか。
小学生から大学生までの年代は、いま述べた「正解はひとつしかない」という思い込みとの闘いです。○×式テストへの回答習慣がしみ込んでいて、これを壊すのは本当に大変。メディアリテラシーでは「決めつけない、思い込まない、いろいろな見方があると気づこう」と教えるわけですが、どうしても「正しい見方はひとつでしょう。それを教えて」とか、「絶対に信じていいメディアはどれなんですか」になってしまう。正解はひとつしかないという教えの呪縛から解くのは、本当に難しいです。日本の学校教育は、大急ぎで見直さないといけません。
とにかく初耳の情報を受信したら、「①即断するな/②鵜呑みするな/③偏るな/④(スポットライトの)中だけ見るな」……4つの頭文字をつないで「ソ・ウ・カ・ナ」を実践すること! それぞれの具体的なHowとして、①情報の“3密”(密閉・密集・密接)チェック、②意見・印象部分の識別練習、③色々なカエル(立場をカエル/重心をカエル/等)の当てはめ訓練、④周囲の暗がりの想像トレーニングなどを体験し、ぐんぐん視野を広げていきます。
次に社会人相手では、新入社員研修を頼まれることが多いのですが、力を入れているのは先ほどの発信者責任です。「君たち、今まではバカッターとかやっても自分が吊るし上げられるだけで終わりだったけど、今日からは『お前はどこの会社の人間だ?』って言われるからね」と言うと、効き目があります。気持ちがリフレッシュされる新入社員のときは、メディアリテラシーを身につける大きなチャンスです。
――40歳以上の中高年向けには、どのように教えますか。
中高年の皆さんは、とにかく手ごわいです。自分はこうやって情報を受け取るんだという流儀を決めているし、一度信じたことを修正するのはプライドが許さない。ほかの情報はデタラメだと瞬間的に決めてしまい、てこでも動かない人がいます。
たどり着いた方法は、模擬授業です。「いまの子どもたちは、メディアリテラシー教育というのを受けています。これは、皆さんの世代が経験していない教育です。ここで授業を再現してご覧に入れますので、皆さんは恐縮ですが中学2年生になり切って、僕が何か言ったら中2っぽく答えてください」そういう設定にするとすんなり聞いていただけて、だんだん真剣にメモを取り始めて下さるという感じです。
授業のあとに寄せられる感想文は、10歳の小学5年生も、経営層向けのセミナーが対象とする60、70歳代の方もそっくりです。「面白かった。自分も今日からやってみたい」――どの年齢の誰もがメディアリテラシー教育を体系的に受けてこなかったことが、感想文が同じだという一点からもよくわかります。
――先ほど(前編で)「メディアリテラシーは、日本の学校教育で場末に置かれている」とおっしゃいましたが、光村図書の小学校5年生の国語の教科書には、下村さんが執筆した『想像力のスイッチを入れよう』というエッセイが採用されていますね。
光村の教科書の僕の文章は、説明文という単元に載っているんです。指導の手引き的に言えば、説明文であれば「AIとは何か」でもいいし、「ポリバケツのできるまで」でもいいという位置づけです。だからメディアリテラシーに関心のない先生たちは、僕のあの文章を機械的に段落に分けて解剖して、「説明文というのは、こういう組み立てでできています」と教えて終わりです。
そういうふうに扱われている授業例を知ると、自分の身体を「これが心臓です。これが腎臓です」と解剖されているだけで、人格はどこへ行ってしまったのかという悲しい思いがします。メディアリテラシーについては、まだまだ、問題意識や関心のある先生だけが実践しているという認識です。とは言え、そういう熱心な先生が徐々に増えてきていることは明るい兆しですが。
――光村の教科書の文章について、熱心な生徒や先生からはどんな反応がありますか。
子どもたちの感想文を先生が送ってくれるのですが、いままでに受け取った反応で一番好きだったのは、「想像力のスイッチは、人生のスイッチだと思います」というもの。情報の受け取り方にとどまらず、人生が広がるというのです。すごいなと感心しました。
もうひとつよかったのは、「まず、下村さんがここに書いていることが本当かどうか考えたい」。どうしても「この文章を読んで、その通りだと思いました」という感想が多い中で、「これは本当なのか」と立ち止まるのは、ソウカナのメソッドを早速使ってくれているということ。嬉しかったです。
先生からの反応で印象に残ったのは、「これを教えちゃったら、われわれはその後すごい覚悟が要りますね」。日本ではこれまで長年、先生の言うことを素直に聞くのがよい子だという教育を続けてきた。しかしこの文章は、鵜呑みにしないことを勧めていて、よい子の定義を変えてしまう教材ではないかと。
――「ワーストの反応」はどんなものでしょう。
「メディアは嘘つきだとよくわかりました。今日から信じないように気を付けます」という反応ですね。
これは、一部の先生方がそういうニュアンスで教えてしまう結果だと思います。教科書の最大の弱点は、それを使って先生がどう教えるかによって、色がどうにでも変わることです。「メディアは嘘つきだ。もう信じない」という子どもたちを大量生産することに、自分の文章が使われるのなら、へこみますね。
だから本当は、この文章を教科書に載せただけでは駄目なんだと思います。そこで、行政単位ごとによく開かれる先生たちの勉強会に出かけて行って、教え方の一サンプルをご披露しています。学校を回って授業をやっていると、先生方から「また来てください」と言われるのですが、「いや、次からはあなた方がやってください」と答えたいのが本音です。僕は種をまいて回っているので、そこに花がどんどん咲いてくれなかったら花畑になりません。
――学習指導要領の中で、メディアリテラシー教育は今後どのように位置づけるべきだと思いますか?
国語の中の1パートではない、と僕は思っています。国語、算数、理科、社会……と並ぶすべての教科を貫く横串が、メディアリテラシーでしょう。情報の受け取り方と発し方は、全教科共通の基盤なのですから。
文科省の動きが遅いなら、登山道の入口はどこからでもいいので、経産省「未来の教室」や新設のデジタル庁などにも頑張ってほしいです。デジタル教育の一環という入り方もあると思います。他の省庁が動けば、縄張り意識が働いて、文科省も熱心な職員(います!)を重用してくれないかと期待してます。
「批判的思考力」という言葉が生む問題
――メディアリテラシーの基本とされる「批判的思考力」は、どうすれば身につくでしょうか。
批判的思考力を付けるためには、「批判的」という言葉をやめたほうがいいと思っています。学校の現場で子どもたちの反応を見ていて思うことです。
「批判的」という日本語の語感は、英語の「クリティカル」と違ってネガティブです。子どもたちは、他人を批判したくないんです。仲のいい友達の言ったことを批判的に受け取ろうと教えても、無理です。そこでブレーキをかけてしまう元凶が、「批判」という言葉です。
数年前の某大学の授業でも、そのことを痛感しました。僕が「情報に付和雷同して何でも信じてしまうと、『そうだそうだ』と言いながら、みんなで崖から飛び降りることになっちゃうかもしれないよ。だからちゃんと立ち止まって、『そうかな』のチェックをしていかなきゃいけない」という話をしました。
すると、ある女子学生がリアクションペーパーにこう書いてきました。
「自分は、『そうかな』なんて批判して仲間から孤立するぐらいだったら、『そうだそうだ』と叫びながら崖から落ちるほうを絶対に選びます」
これは僕には衝撃で、翌週の授業で「こういうリアクションがあったんだけど」と紹介しました。すると、さらにその週のリアクションペーパーに「私も同感です」「孤立するぐらいだったら、みんなと一緒に落ちるほうがいい」という意見が相次いだのです。
日本がこういう社会で、そんな空気の中にいる若者に向かって、「批判的に」なんていう勇ましい正論を吹っかけても通用しない。一緒になって「そうだね、そうだね」と言いながら、少しずつ向きを変えていかなければ駄目だなと思ったのです。
つまり「No, but」ではなくて「Yes,and」です。いったん受け入れてから窓枠を広げて、他の景色も見えるようにしていくやり方です。これなら日本人は得意ですから。
――「クリティカル」には「吟味する」という意味もありますから、確かに「批判的」という訳語には問題がありますね。ただ、相手の意見を批判したり反論したりすることは、相手の人格を否定することではないと教えてもよいのでは。それを避けると、『根治治療』にはならないのでは?
ええ。活発な学校、自立心の強い生徒たちなら、そのように根本から伝えていく方法をこそ採るべきでしょう。ただ、これまで多くの生徒を教えてきた僕の皮膚感覚でいうと、そういうタフな方法では実践を避ける生徒の方がずっと多いです。
「批判し合うことは大事だ」という正論で通じる人たちが相手ならいいのですが、それだけで授業していると、一番そういうことをわかってほしい人たちに届きません。フェイクニュースやQアノンに従うような人たちには、わかってもらえないと感じるのです。「窓枠を広げる」練習をするのが、むしろ根治治療なのでは、と思っています。
山を上るには幾つものルートがありますが、「批判」という言葉を使わずして山頂にたどり着ける道を僕はガイドしたい、ということです。
現実のニュースを教材にしよう
――今後、メディアリテラシー教育は、どう展開されるべきでしょうか。
一定期間に集中したカリキュラムで教えて終わりにするのではなく、日常化する必要があります。何年生で教えると決めるのではなく、常にやっていくことです。先生が朝の会などを利用して、「今ネットで流れてるあの噂、どう思う? ソ・ウ・カ・ナ?」と問いかける習慣が大事です。
2020年1月にワシントンで、連邦議事堂襲撃事件が起こると、アメリカの先生たちは翌日から「私はこんなふうに教えた」とネット上で報告を始め、「こういうふうに生徒たちに問いかけましょう」という情報交換がすぐ始まりました。日本では時事問題を教室へ持ち込むのを避けようとしますが、先生たち自身もHowがわからないから、無難に避けてしまっているわけです。こうやれば導入できるという方向性の提案をしていくことが必要です。
偏らずに時事問題を教材化できる方法は必ずあるはずで、生き生きした現実の情報のほうが、メディアリテラシーの眼力は格段に身につくでしょう。まだ新しい教科ですから、「こうやったらうまくいった」というノウハウを、もっと交換していくことも大切でしょう。そのために、スマートニュースさんの作ったこの研究所のサイトがハブになってもいいと思います。
もう1つ、授業の内容としては、制作体験も有効です。映像制作でもブログでもいいのですが、自分で発信する体験を強化していくことが必要です。GIGAスクール構想でクラス全員に端末が行き渡るようになったら、動画制作授業の大チャンス到来です。昔からNIE(Newspaper in Education)といった形のメディア教育はありましたが、映像系は道具が高価なために実現できませんでした。そのネックが、いよいよ解消されるわけです。
動画制作の授業を見ていて、いつも感じることがあります。文章を書かせようとすると、鉛筆を持ったまま「書けない」と言ってじっとしてしまう子がいるものですが、ビデオカメラを持って「録画ボタンが押せない」と言っている子はいません。着手する敷居の低さが、まるで違うのです。
しかもスマホやタブレットの中だけで編集まで完結してしまうので、編集ソフトを入れたパソコンすら不要です。いまの子どもたちはビックリするぐらい、たやすく使いこなします。ユーチューバーが小学生の憧れの職業ですから、苦手意識がないのです。
とにかく撮ってみて、「あ、こういうふうに撮ると誤解されるんだね」とか「実際と違った印象になっちゃうんだね」と作り手の経験を重ねることによって、受け手としての眼力もついていきます。
道具が揃ったら、必要なのは指導者です。先生たちは映像を扱う体験を持ってないわけですが、いまは各地にケーブルテレビや映像制作会社があるし、テレビ局のOB、OGもいます。そういったスキルを持つ人たちに、まず教え方を教えます。つまり「子どもたちがどんな撮り方をしても『そうじゃない』と言わず、まず撮らせてみて、気づくまで待ってください」等、教育の基本を学んでもらうのです。その指導者養成の枠組み作りや予算の手当ては、文教族の議員や文科省に政策として求めていきたいところです。
2020年からコロナが蔓延して、デマに振り回される人が増えました。「トイレットペーパーがなくなるらしい」とか「ぬるま湯を飲むと感染しないらしい」といった噂がSNSで拡散されて、デマ情報に感染しない抗体を身につけることは誰にとっても切実な問題になりました。メディアリテラシー教育のニーズは、ぐんと高まったのです。
由々しき事態によってニーズが高まったのは皮肉ですが、リテラシー教育にとっては、ピンチはチャンスと捉えるべきでしょう。