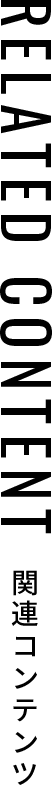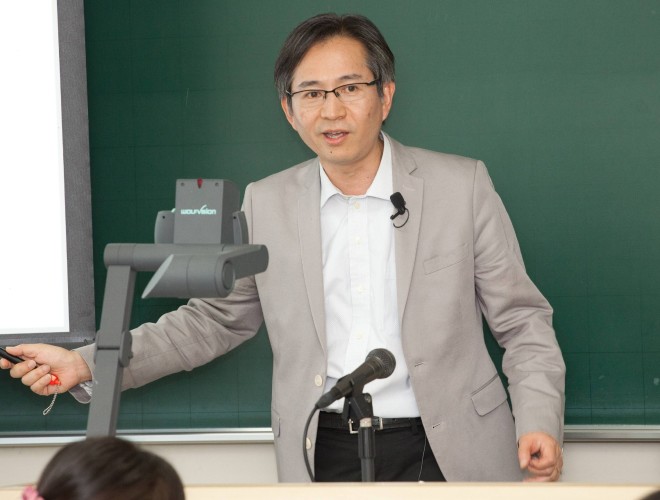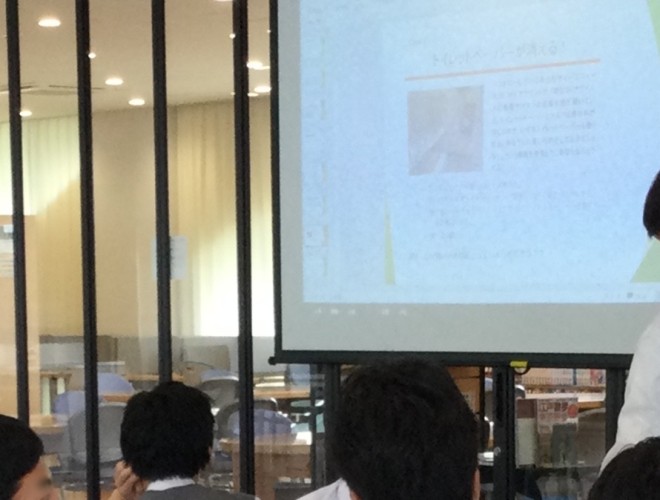TBSのアナウンサー、フリーのキャスター、そして官邸での広報経験を経て、いまは大学で教鞭をとりつつ、個人事務所を立ち上げて活動する下村健一さん。日本におけるメディアリテラシーの実践の先駆者として、小学生から社会人まで、幅広くメディアリテラシーについて教えてきた。下村さんを駆り立てるものは何か、教育をどう変えたいのか、インタビューした。(聞き手:山脇岳志、石井謙一郎、長澤江美)
下村 健一
令和メディア研究所 主宰・白鴎大学特任教授・JIMA(インターネットメディア協会)リテラシー部会担当
1960年生まれ。東京大学法学部政治コース卒。TBS報道局アナ、フリーキャスター計25年を経て、官邸にて内閣審議官等を2年半。慶應義塾大学特別招聘教授などを満了後、現職。光村図書の小学校5年の国語教科書に「想像力のスイッチを入れよう」を執筆している。これまで、小学校~大学、企業などで、数百回のメディアリテラシー授業を行ってきた。
ミニコミ紙で父をネタにしようとして、母に怒られる
――メディアリテラシー教育に携わるようになったきっかけはありますか?
幼少時からのさまざまな経験がきっかけになっています。
まずは5歳のときです。お向かいに住んでいた同級生の男の子と、いまでいうミニコミ紙を創刊しました。その子の弟の名前を借りて「としちゃんタイムズ」。町内のどこのどぶ板が外れたとか電柱が傾いているとか、新聞の折り込み広告の裏に書いて、ご近所のお母さんたちに回覧していたんです。その都度、「どうだった?」と感想を聞いて、みんなが読んでくれる記事の書き方をなんとなく覚えていきました。
小学校5年生のとき、70年安保で東大安田講堂の籠城事件が起こります。僕の父親は、東大の駒場で教官をやっていました。あの時期、駒場でも教室に先生を軟禁して一晩中吊し上げたりしていたのです。ある日、大学当局から我が家に電話がかかってきました。母が取って真っ青になって、「お父ちゃんが缶詰めになっちゃって、今日は帰って来られないかもしれない」と言いました。
その瞬間、僕は飛び上がって「やったー、『としちゃんタイムズ』特ダネ!」とはしゃぎました。すると、僕に声を荒らげることなど一回もなかった優しい母に、「何言ってるの!」と本気で叱られたのです。
二重に衝撃を受けました。ネタができたとまず喜んだ自分に驚いたこと。母親の反応を見て、何だか知らないけど、新聞は人を怒らせることがあるのかもしれないなと感じたこと。メディアの怖さを知った原体験です。
中学生のときには、我が家に近い同級生の女の子の家で、先進国最後の天然痘が発生しました。当然大騒ぎになって、メディアが殺到しました。僕たちはその家を遠巻きにしながら、なんとなく浮き足立っていました。
ところが新聞記者のカメラがこっちを向いた瞬間、僕も含めて近所の人たちは、不安げに見守る近所の住民、の顔をするんです。頼まれてもいないのに。少なくとも僕は、そのほうが新聞に載れるだろうという計算がパッと働いてました。
「世の中の出来事って、こうやって作られていくのかな」と、瞬間的に演じた自分の表情から、後日考えました。それ以降、事件のニュースを新聞やテレビで見るたび、あのときの自分を思い出して、「ああ、いま映っているこの人たちも少し演じてるのかも」と思うようになったんです。
我が家で取っていた大手の新聞には、「隣の主婦」の言ってもいないコメントが載ったことも衝撃でした。
大学生のときは、学習塾で中学3年生を教えていました。そこへ通ってくる生徒たちの中学校で、先生が生徒をナイフで刺してしまうという事件が起こりました。校内暴力が荒れ狂っていた時代だったせいもあって、大きなニュースになりました。
僕は生徒たちから相談を受けたり、ぼやきを聞かされました。彼らが口々に言ったのは、「テレビや新聞は、学校へ来て校舎の割れたガラスだけ撮っていく。ほとんど割れてないのに、割れているガラスだけ映して『これがこの中学校です』と言っている。『エッ、これ、どこの荒れた学校?』と思うぐらい、そこだけが強調されている。何をやってるんですか、テレビや新聞は?」。僕は答えに窮してしまいました。
松本サリン事件で抗議が殺到
――TBSに入局されてから、印象に残っていることは?
そんな体験があったので、TBSに入社してから、自分は気を付ける伝え手になろうと思っていました。
1994年、松本サリン事件が発生します。ご存じのように、現場近くに住んでいた会社員の河野義行さんが犯人扱いされました。長野県警の捜査一課長が記者会見で「第一通報者宅を家宅捜索。令状の容疑は殺人」と発言したのですが、容疑を“殺人”とする確たる根拠を言わないのです。しかしメディアはお祭り騒ぎになって、「河野容疑者は」と言っているリポーターまでいました。
僕もその会見場を出てすぐ河野宅の前に直行したのですが、河野さんの名前はリポートで出さず、信頼関係を築いてから単独インタビューを放送しました。すると、視聴者から抗議の電話が殺到しました。「なぜ人殺しの肩をもつのか。亡くなった人や遺族の気持ちも考えろ」自分でそんな電話を受けたときは、「遺族の無念を考えるから、ちゃんと犯人を捜しましょう、決めつけないで考えようと言っているんじゃないですか」と答えるのですが、全く聞く耳をもってくれません。
抗議してくる人たちは、正義感に火がついてしまっているからです。正義の暴走ほど怖いものはありません。嘆き悲しむ遺族に代わって、我々が河野義行さん及びその言い分を伝えるTBSと下村を成敗してやる。そんな義憤に駆られているのです。
これは怖いなと思いました。主流と違う意見を言ったら非国民という扱いを受ける状況は、戦争当時と変わっていないと強烈に感じました。
情報の受け止め方をしっかり皆が鍛えていかないと、この国の未来は大変なことになると考えました。
――それでTBS在籍時から、メディアリテラシーに関わる活動をしていたのでしょうか?
社員の間は忙しくて、なかなかできませんでした。辞表を出したのは1999年3月で、ニューヨーク支局にいました。退職する日、筑紫哲也さんの『NEWS23』に出した10分強のリポートが、「カナダにはメディアリテラシーという教科があります」という内容です。メディアの人間が「メディアを鵜呑みにしてはいけません」と言うのは駄目だろうと思っていたので、自分も視聴者側に回る境目の日を狙ったのです。
一番最後に、「その国の政治のレベルは、その国の有権者が決める」という有名な言葉のフリップを出して、めくると「その国のテレビのレベルは、その国の視聴者が決める」と書いてある。それをラストメッセージとして、TBSを辞めました。
その後は市民メディアアドバイザーという肩書を自称して、メディアリテラシーの取り組みを始めました。
専門家の限界
――東日本大震災による福島第一原発の事故のときには既にメディアを離れ、官邸勤務でしたね。
1号機で最初の水素爆発が起こった瞬間、僕は総理執務室にいました。原子力保安院や東京電力から幹部が来ていたのですが、誰にとっても想定外の出来事でした。彼らが揃って断言していた唯一のことが、「5重の防護があるから、爆発は絶対に起きません」だったのです。
ドーンと建屋が吹っ飛ぶ光景をテレビで見て、専門家たちは文字通り頭を抱えてしまいました。そのとき、地元の住民の不安を鎮めるために安全神話を唱えていたのではなく、彼ら自身が本気で信仰していたのだということがわかりました。
ところが30秒くらいするとムクリと起き上がり、何が起こったのかという仮説をとうとうと語り始めます。僕はそれをノート1ページ埋まるぐらい書き留めながら、彼らは30秒考えればわかることを、そのときまで50年考えずに怠って来たのだと悟りました。
想定しなかったのは、情報を決めつけていたから。「他の可能性はないかな」と視野を広げてみるというメディアリテラシーの基本が、この超一流の方々にはなかったのです。
その後、東電から全く情報が届かないという構造的な問題のほか、政府部内にもいろいろなコミュニケーション不全がありました。官邸は状況を全て正確に把握しているはずだと牧歌的に信じている人々からは、本当にわからないことまで「隠している」と批判されました。
何がわかって何がわかってないかを的確に発信する政府の術も、国民側の受信力も、共に乏しかったために、あの大混乱が起こってしまったのです。内閣広報室審議官としての己の非力を猛省すると同時に、もっと情報の受信力や解釈力を国民皆が付けないと、この先何か窮地に立ったとき、日本は他国から大きく後れを取ってしまうと感じました。メディアリテラシーは《あるといい》ではなく、《ないと危険》だという確信をさらに強めました。
「べき論」だけ教えるのはやめよう
――下村さんは、小学生向けの授業から経営者向けの講座まで、メディアリテラシーを幅広く教えています。共通して気を付けていることはありますか?
「情報に振り回されないように気を付けましょう」とか「真偽を見極めましょう」と言われても、「よーし、今日からそうしよう」と実行できるものではありません。お題目やスローガンは、何の役にも立ちません。
1番目にして最大の留意点は、「Should」に流れず「How」に徹することです。どうやって気を付けるのか、どうやって見極めるのか、具体的方法を覚えてもらう。いったん習得してしまえば、意識せずにできるようになるからです。
例えば私たちが道を渡る前に右と左を確認するとき、いちいち意識していないはずです。小さい頃に教え込まれたことが、習慣として身についているのです。だから「情報に接するときも同じで、最初は『右や左(=周囲の情報)も見よう』といちいち言われるけれども、自然にできるようになるから大丈夫だよ」と僕はいつも励ましています。
メディアリテラシーの授業は、教育の主軸であるべきなのに、未だ場末に置かれたままだと感じます。その一因は、HowではなくShouldで終わっているコンテンツが多いからではないでしょうか。もっともらしい「べき論」だけ唱えても、「そんなこと分かり切ってるよ」と軽んじられるだけですから。実際、メディアリテラシー教育に不熱心な先生に消極的な理由を尋ねて、そういう答えが返ってくることが何度もあります。
2番目の留意点は、ほかの科目のように先生と生徒が向かい合って教え教わるのではなく、横に並ぶ関係を作ることです。メディアリテラシーは他の教科と違って、先生たち自身にも僕自身にも、教わった体験がありません。自分が教わっていないものを、子どもたちに教えようというのは、無理があります。ですから僕自身も含め、目の前に新しく現れる情報の方を生徒たちと一緒に向いて、共に考えていく姿勢が大切です。
そんな先生の姿を生徒が横から見れば、「ああ、初対面の情報にはこういうふうに向き合えばいいのか」と気付く。教える教わるではない授業の形が、メディアリテラシー教育の特徴になると思います。いま、文科省が「主体的・対話的」な学びの旗を振る方向にあるのは、これと合致していると思っています。
3番目は、メディアリテラシーは古来の狭義の「メディア」(報道機関など)に対抗する技だと思われがちな誤解を解くこと。「メディアという厄介者がいて、情報操作や印象誘導をしてくるから気を付けましょうね」という防衛的な構えになりがちなのです。もちろん、メディアの特性や構造を学ぶリテラシーも大事ですが、いま必要性が切迫しているのは、もっと広い意味の、土台としての情報リテラシーです。実際にユネスコなども、最近は「メディア・インフォメーション・リテラシー」だと言っています。
「間違った発信をするメディアが悪いのだから、メディアが自らを正せばいい」「こちらは言われたことをそのまま信じるから、メディア側が責任をもって完璧な情報を出せ」という考え方に立つと、受信者としての自分の責任を免除してしまうことになります。
情報の送り手と受け手の間にキャッチボールが成立するためには、投げる人だけでなく取る人も相応の責任を負う必要があります。ボールを受け取る側には《受信者責任》があることを、自覚しなければならないのです。
しかも現代社会では、誰もが情報の発信者でもあります。SNSなどで受け取った情報をそのまま転送して拡散させたり、「いいね!」を押すだけの行為にも、《発信者責任》が伴います。
―――後篇では、下村式授業の具体的なHowとは何か、尋ねます。
下村健一さんインタビュー(後篇)はこちら