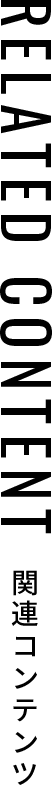米国における、共和党支持者の科学不信の背景には何があるのか。また、そうした人たちに科学リテラシーを語る際、求められるのはどのような情報、姿勢なのか。
『ルポ 人は科学が苦手』の著者で、読売新聞・米ワシントン特派員として大統領選挙や科学コミュニケーションなど多くの取材を重ねた筆者が考える、科学に基づく共通理解醸成への道筋とは。
冒頭の写真:全長155メートルの「実物大・ノアの方舟」。方舟の近くにいる人と比べると、その巨大さがわかる(2017年7月、ケンタッキー州)=三井誠撮影
三井 誠
読売新聞東京本社英字新聞部次長
1994年、京都大学理学部卒業。読売新聞東京本社に入社後、科学部で生命科学や環境問題、科学技術政策などの取材を担当。2013~14年、米カリフォルニア大学バークレー校ジャーナリズム大学院客員研究員(フルブライト奨学生)。15~18年、米ワシントン特派員として大統領選挙や科学コミュニケーションなどを取材した。米国の科学不信の状況などをまとめた近著『ルポ 人は科学が苦手』(光文社新書)で「科学ジャーナリスト賞2020」を受賞。2020年から慶應義塾大学大学院理工学研究科非常勤講師、21年から日本科学技術ジャーナリスト会議理事も務める。
分断が進む米国に見る科学リテラシー普及への道筋(前篇)はこちら
科学不信の背景
ワクチンやマスクを拒否したり、地球温暖化を否定したり――。共和党支持者の科学不信の背景に何があるのか。

出典:『ルポ 人は科学が苦手』(光文社新書)
ウィスコンシン大のゴードン・ゴーチャット博士が2012年に発表した論文*は、数十年に及ぶ世論調査結果を分析し、1990年代以降に、保守的な政治信条を持つ人が科学への不信を募らせていった状況を描き出している(図2-1)。
その背景の一つとして、地球温暖化や生物多様性の減少など、科学が産業活動に伴う環境の悪化を明らかにし、規制作りを促す要因になり始めたことが指摘されている。ゴーチャット博士は論文で、「科学が急速に政治色を帯びてみられるようになり、政治から距離をおいた存在ではなくなった」と指摘した。「小さな政府」を志向する共和党勢力が、規制につながる成果を生み出す科学を疎ましく思うようになったのだ。
ゴーチャット博士の論文で、科学への不信を募らせる人たちに共通する特徴が、保守的な政治信条のほかにもう一つあった。それは教会に行く頻度だった。教会に頻繁に行く人ほど、科学への信頼が低下していたのだ。その原因の一つに、創造論と進化論を巡る攻防がある。
聖書の記述を重視する人たちは今も創造論を信じ、科学が提示する進化論を否定する。米ギャラップ社の世論調査(2019年)によると、米国では今も4割の人が創造論を信じている。米国には、聖書の世界を再現し、創造論を擁護するテーマパークのような施設すらある。2007年に開館した創造博物館(creation museum)(ケンタッキー州)では、「進化論は洗脳だ」とガイドが訴え、複製化石の展示紹介文には「神が創造した」と記載されていた。アダムとイブの模型もあった。

さらに、創造博物館から車で1時間ほどの小高い丘の上には、地上の動物を大洪水から救ったという「ノアの方舟」が、聖書に基づいて「実物大」で復元されていた(左写真=
進化論だけでなく、人工妊娠中絶や生殖補助医療など、子供の誕生に医療技術で介入することへの反発も強い。こうした人たちのなかで、特に科学への反発を強めているのは、「福音派(エバンジェリカル)」と呼ばれる、伝統を重んじる保守的なグループだ。福音派は米国の人口のほぼ4分の1を占める最大の宗教勢力で、共和党の有力な支持母体でもある。

出典:『ルポ 人は科学が苦手』(光文社新書)
規制を嫌う産業界と、宗教的な価値を重んじる福音派が、期せずして「科学不信」という旗印で結びつき、共和党の強固な支持基盤を作りだしている。科学と社会の関係に詳しいジャーナリストのショーン・オットー氏は「福音派と産業界との政略結婚」(図2-4)と表現する。
一方、科学者の団体のなかにも政治的な偏りを感じることがあった。2018年2月にテキサス州オースティンで開かれた全米科学振興協会(AAAS)の年次大会でのことだ。AAASは科学誌サイエンスの発行元で、世界最大ともいわれる科学者の団体だ。年次大会では最先端の科学成果が発表されるだけでなく、科学と社会にかかわる問題も幅広く議論される。この年の大会には、約1万人が参加した。そのなかで、最も大きな会場で行われる講演会に、ジョー・バイデン氏が登壇した。当時は大統領選への出馬表明こそしていなかったが、出馬が有力視されていた。バイデン氏は、科学軽視のトランプ政権を批判し、会場から喝采を浴びていた。政治的に中立なはずの科学団体だが、次期大統領選の民主党の有力候補予定者が他党を批判して拍手に包まれる姿を見て、科学者自身が共和党勢力を締め出しているかのような印象を受けた。
科学者がリベラルな政治信条に偏っていることを感じた場面はほかにもある。例えば、トランプ政権の事実軽視の姿勢に反発した科学者らが2017年4月、全米各地で行った「科学のための行進(March for Science)」だ(前篇冒頭の写真)。研究室を飛び出した科学者らが、思い思いのメッセージを込めたプラカードをかかげ、科学を重視する姿勢を訴えた。プラカードにはこんな言葉があった。
「Stand Up for Science(科学のために立ち上がれ)」
「Evidence not Ideology(イデオロギーではなく証拠を)」
「Keep America Factual(事実に基づくアメリカを)」
主会場となったワシントンでは、主催者見積もりで約10万人が参加した。メリーランド大学の研究者が行ったアンケートで、参加者の政治信条を見ると、「保守」と答えた人はわずか5%で、「リベラル」と答えた人が83%に上った。
敵か味方か
統計数字だけでは実感がわきにくい政治による分断だが、現場取材では、それを肌身で感じた。

2018年8月、南部アラバマ州の炭鉱を訪れ、そこで働く人たちの話を聞いた。炭鉱は2014年に閉鎖されたが、石炭業界の再興を訴えてトランプ氏が当選したことを受け、再開されていた。地球温暖化対策として規制がかけられていた石炭業界だったが、トランプ氏が大幅な規制緩和を進めるとの期待が高まっていた。炭鉱を経営するランディー・ジョンソンさんは、炭鉱再開にあたって購入した270万ドル(約3億円)の掘削機に、特注で白く「TRUMP」と書きこんだ(左写真。手前でポーズをとるのがジョンソンさん=三井誠撮影)。2018年6月にはホワイトハウスのトランプ大統領宛てに手紙を送った。「戦いを続けてくれ。俺たちはこれからも応援する」とつづった。
ランディーさんに地球温暖化への考えを聞いてみると、こんな答えが返ってきた。
「オバマ政権は、自分たちが言ってほしいことを言う科学者を雇って、大金を払った。民主党は地球温暖化の将来を語ることで、人々を怖がらせている。でも、俺は地球温暖化を信じない。結局は、どっちの側を信じたいかという話だ。俺は共和党を信じるよ。そして、共和党の応援を続ける。今の流れを続けることが大事だ。それができなければ、俺たちは敗者になる」
ジョンソンさんは「結局はどちらの側を信じたいかという問題だ(It's just a matter of which side you want to believe)」と、敵か味方かという構図で地球温暖化問題をとらえていた。そういう考え方をしている人たちに、科学リテラシーを説いたところで、伝わらないだろう。AAASの大会にバイデン氏が参加したことを知れば、「温暖化を訴える科学者の団体が、民主党の支持者の集団である証拠だ」ときっと、反発を強めただろう。ジョンソンさんにとって、地球温暖化を巡る問題は、炭鉱経営という自らの生活に直結した問題だ。「国のエネルギーを支えている」との自負も持って働いてきたジョンソンさんの思いを、「科学リテラシーがない」と切り捨てることはできない。
炭鉱で働く人たちのなかには、「炭鉱閉鎖のためにほかの州に働きに行かなければならなくなったが、炭鉱再開でまた地元で働くことができ、家族で安定して暮らせるようになった」と笑顔をみせる人もいた。
「敵か味方か」の構図のなかで、議員の職を失った人もいた。
共和党下院議員(南部サウスカロライナ州選出)だったボブ・イングリスさんは2010年の選挙の前に、地球温暖化を疑うことをやめた。そして、共和党の候補者を決める予備選挙で新人に敗れた。予備選で敗れれば共和党候補として戦うことができず、議員への道は事実上たたれる。現職が予備選で敗れるのは異例だった。予備選では、温暖化に理解を示したイングリスさんを排除するため、石油業界などが保守系の政治資金団体を通じて選挙資金を投入し、温暖化を疑う対立候補を支援した。
イングリスさんは言う。「地球温暖化を認めたことで、私は共和党という部族(tribe)のなかで異端の存在になってしまった。2010年は(リーマンショック後の)世界的な経済危機のなか、人々はそれぞれが属する部族により忠誠を尽くすようになっていた。厳しい時だからこそ、グループのみんながまとまって乗り切ろうとしていた。そんな時に、民主党と歩調を合わせる主張をしたことは、裏切り者と見なされた」
イングリスさんが使った「部族(tribe)」という言葉は、直接的で生々しく聞こえた。政党のメンバーがお互いに強い絆で結びつき、まるで「部族」のような集団になっているのが、米国政治の現状だ。政治的な理念よりも、「敵か味方か」で選別するようなあり方は、リベラルな発想では批判の対象だったが、家族や仲間を大事にして働く炭鉱の人たちを思い浮かべると、批判するばかりではお互いの理解は進まないだろうと感じた。
米国の科学不信の現場については、拙著『ルポ 人は科学が苦手』(光文社新書)でも詳述しているので、興味がある人は読んでみてほしい。
* * *
米国で進む政治的な二極化は、科学にとどまる問題ではない。メディアにも大きな影響を与えている。トランプ前大統領は、CNNやニューヨーク・タイムズなどを「フェイク・メディア」を決めつけ、集会で喝采を浴びた。FOXニュースなど保守系メディアは、地球温暖化に懐疑的なニュースを流すなど、分断が広がっていた。
情報の送り手の意図を検討したり、情報の精度に気を配ったりするメディア・リテラシーが求められる現代だが、そもそも、自分の趣向にあう情報を送り届けてくれるメディアを選び、その情報に「そうそう」と相槌を打つばかりであれば、あるべきリテラシーと現実との溝は広がるばかりだ。
信頼と共感で論理に架橋する
では、どのようにその溝は埋められるのだろうか。相手の感情に気を配り、共感を得ながら情報を伝えようとする試みから、そのヒントを探ってみたい。
先ほど紹介したAAASの大会で、「もう一つの事実と偽ニュース~事実だけでは不十分なとき」とのタイトルで行われたセッションでは、トランプ政権下で事実を軽視する動きにいかに対応すべきかが話し合われた。司会を務めたマーク・バイヤー氏は、連邦議員のスタッフを20年にわたって務め、「人を説得する仕事をしてきた」と自己紹介した。バイヤー氏は、古代ギリシャの哲学者アリストテレスの言葉を引用して、情報を伝える上で重要なことを紹介した。
「アリストテレスは演説に大切なものとして三つを上げた。一つはロゴス(Logos=論理)。論理的であり、事実であるということだ。これは実は3分の1でしかない。アリストテレスが次に上げたのはエトス(Ethos=信頼)だ。聞き手と話し手の関係であり、話し手の信用の問題だ。私はこのセッションを自己紹介から始めた。議会で20年働いた経験があり、『この人は何かを知っており、話を聞く価値がある』と思ってもらうためだ。三つ目はパトス(Pathos=共感)だ。この三つの要素が効果的なコミュニケーションに必要だ」
科学者が冷徹な論理にしたがって事実を話しても、「信頼」と「共感」がなければ、うまく伝わらない。「事実は必要だが、十分ではない」。バイヤー氏はそう指摘した。
近代科学は、実験や観察できめ細かく事実を突き止めるのが特徴だ。「事実」は近代科学にとってアピールポイントであるはずなのに、実は、その事実の力が強すぎてコミュニケーションに失敗しているのではないかと感じた。事実に頼りすぎて、アリストテレスが挙げた「信頼」と「共感」に考えが及ばないのではないだろうか。社会のなかで科学リテラシーを高めるには、こうした点も踏まえたコミュニケーションが求められる。
伝え方に気を配る情報発信の例をもう一つ。先ほど紹介した、地球温暖化への理解を示して落選したイングリスさんの活動だ。イングリスさんは落選後、保守的な政治信条を持ちながらでも、地球温暖化対策を進められることを伝えようと、2012年に非営利団体を作った。
地球温暖化対策は、二酸化炭素の排出枠の設定など大がかりな規制を伴い、民主党が支持する「大きな政府」を連想させがちだが、イングリスさんは、規制を強化しなくても対策が可能であると訴えている。市場原理に基づく競争で技術革新を進めて温暖化対策につなげる可能性や、化石燃料に課税する炭素税を創出してもほかの減税を組み合わせることで「小さな政府」を維持しながら温暖化対策を進められることを強調する。
「知識は心を通って頭に届く(The path to the head runs through the heart)」。上から目線でリテラシーを説くのではなく、イングリスさんは保守系の人たちに共感を得ながら温暖化対策を伝えようとしている。
科学やメディアが「政治の色」に染まったままで、人々が自分の好みの色に包まれて心の安定を得ている状況では、科学やメディアを巡るリテラシーは浸透しないだろう。まずはお互いを理解しあおうとする姿勢が求められる。「リテラシーがない」などと相手をさげすむような姿勢では、溝が埋まらないばかりか、広がる結果になる。
「ワクチンで不妊」とどう向き合うか?
新型コロナウイルスのワクチン接種を巡っては、接種率が人口比で7割に近づくと足踏み状態となる「7割の壁」に先進各国が直面している。ワクチンへの拒否感、安全性への疑問などが、「壁」を生み出しているとされる。本稿の前半では、陰謀論からのワクチン拒否、「不妊になる」といった安全性への不安、政治信条に伴う米国での反発を紹介した。本稿の結びとして、こうした人たちと、どのようにコミュニケーションをしていけば良いか、考えてみたい。
参考になるのは、保守的な人たちが多いキリスト教福音派に属しながらも、地球温暖化の研究者であり、さらに温暖化対策の重要性を伝える活動を続ける米テキサス工科大のキャサリン・ヘイホー教授の指摘だ。
自らも福音派の信者であることから、ヘイホーさんは信仰を共有して、保守的な人たちにメッセージを伝えようとしている。そうした活動から見えてきたのは、地球温暖化に懐疑的な主張は、本心を隠す「煙幕」(図4-1)に過ぎないではないかという視点だ。
温暖化に懐疑的な人たちはこんな主張をする。
「地球温暖化は起きているかもしれないけれど、人間の影響かどうかはわからない」
「地球温暖化が進んだらシロクマは困るだろうが、私たちには関係ない」
ヘイホーさんはこれらの主張を「本当の意図を隠す煙幕だ」と指摘する。 戦場で味方の動きなどを隠す人工的な煙が煙幕だが、ヘイホーさんがいう煙幕は、「小さな政府」を志向する保守的な人たちが「規制が嫌い」という本当の意図を隠すために使う、目くらましのようなものだ。「規制が嫌いだから」とそのまま言うと、わがままなだけと思われるので、「地球温暖化の科学は疑わしい」という「煙幕」を使っているという構図だ。

出典:『ルポ 人は科学が苦手』(光文社新書)
世界の科学者らで作る「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の第6次評価報告書が8月に発表され、人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことは、「疑う余地がない」(unequivocal)と指摘した。しかし、温暖化の現状や今後の気候状態については、「very likely(90–100%)」「likely(66–100%)」などの一定の幅の確からしさをもとにしか推計できない。コンピューターで模擬計算するにしても、複雑な気候を完全に再現することはできず、常に議論の余地は残る。こうした不確実性を理解することも科学リテラシーの一つだろう。そして、これらの不確実性を踏まえても、対策が必要なレベルにまでリスクが高まっているというのが国際社会の現状認識だ。
一方、懐疑派の人たちが「温暖化の不確実性」を指摘するのは、科学的な問題点を明らかにして予測の精度を上げる目的ではなく、自分たちの思いを実現するための口実に使っているだけなのかもしれない。だから、煙幕を真正面から受け止めてデータや事実を積み上げて説得しても、議論は空回りになるだけなのだろう。
新型コロナウイルスのワクチンに否定的な立場をとる人たちの主張も、もともとの本心ではない、表向きの煙幕なのかもしれない。だとしたら、なぜ、そのような考えに至ったのか。煙幕の向こうにある気持ちに思いを馳せる必要がある。
「政府や自治体への反発なのか」
「製薬企業あるいはマスコミへの不信感なのか」
「自然志向が強く薬全般への拒否感なのか」
「身近な人の発言に影響を受けているのか」
彼らあるいは彼女らの気持ちに寄り添いながら、科学リテラシーを語ることが大事なのだと思う。
* Gauchat, Gordon(2012). “Politicization of Science in the Public Sphere: A Study of Public Trust in the United States, 1974 to 2010”, American Sociological Review, 77(2), pp. 167-187.
※本稿では、拙著『ルポ 人は科学が苦手』(光文社新書)の一部を抜粋し、内容に含めています。